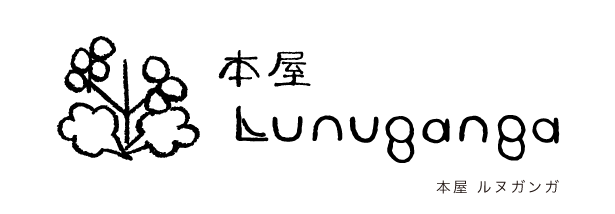-

【サイン本】自炊の風景
¥1,760
版元:NHK出版 著:山口祐加 四六判並製 208ページ 2026年1月刊 生活も人も料理も毎日少しずつちがう。その日にしかない偶然があるから、自炊は面白い 食、暮らし、旅、家族・友人などさまざまな場面で料理の片鱗に触れて心が動いた瞬間を、ありのままに綴った自炊料理家・山口祐加初のエッセイ集。初めて料理をした7歳の頃から、料理家としての独立を経て、世界の自炊を求めて海外を訪ね歩いた現在までに食べてきた食卓の数々の風景を凝縮し、豊富な写真とともに17のレシピも収載。「自炊」にとことん向き合い、著者と料理との関係性を浮き彫りにする、いま最注目の料理家の日常の記録。
-

nice things 83 まだ見ぬ景色と、まだ見ぬ自分と出会う。旅の宿。
¥1,980
版元:情景編集舎 A4変形 124ページ 2026年1月刊 日常の景色は変わるもの。 日常の輪郭も揺らぐもの。 あなたの景色はどうですか? 今日の自分はどうですか? 明日の自分はどこに向かっていますか? 日常の縁(へり)を歩くように旅する。何かを感じる宿の特集です。
-

女性が建てた家と間取り
¥1,980
SOLD OUT
版元:エクスナレッジ 著:田中厚子・松下希和 A5判並製 144ページ 2025/12/26刊 小説家、画家、女優、デザイナーの モダンな住まいを拝見! 女優や作家などの職業をもつ女性が登場すると、 女性が主導して家を建てるケースが 見られるようになる。 茨木のり子、いわさきちひろ、水の江瀧子、 桑沢洋子、宇野千代、林芙美子、吉屋信子、 川上貞奴etc.…… 彼女たちが手に入れた住まいは、 これまでの慣習にとらわれない 新しいライフスタイルを象徴するものだった。 【目次】 第1章 女性と建てる理想の家 ・茨木のり子 ・いわさきちひろ ・エロイーズ・カニングハム ・土浦信子 第2章 憧れのモダンなライフスタイル ・水の江瀧子 ・桑沢洋子 ・宇野千代 ・三宅やす子・艶子 第3章 新しい和のデザインへの探求 ・坂西志保 ・林芙美子 ・吉屋信子 ・川上貞奴 (番外編) ・女性画家たちのアトリエ 三岸節子、仲田菊代、上村松園 ・女性実業家と建築家 廣岡浅子、羽仁もと子、馬場はる (コラム) ・日本の女性建築家はいつ現れた? ・婦人雑誌がつくった住まいの理想像 ・和洋のはざまに揺れた日本の暮らし
-

【特典付き】スペクテイター 55 にっぽんの漂泊民
¥1,320
版元:エディトリアル・デパートメント B5変型 160頁 2026年1月刊 かつてこの国には、社会の枠の外側でひっそりと、しかし確かな意志をもって自由に生きた「漂泊民」と呼ばれる人々がいた。 彼らはいつ、どこから現れ、どのような道を歩んだのか。 個人の行動が可視化され、管理が加速する現代において、定住を拒む「漂泊」という生き方は、いかなる意味を放つのか。 日本の歴史と民俗を辿り、現代人が失った精神の根源を掘り下げる、あらたな旅への案内。 *導入まんが「漂泊民って、なんだろう?」アシタモ *図解「絵でみる漂泊民」河井克夫 *インタビュー ・「サンカの民ってなんだろう?」磯川全次(在野史家) ・「人はなぜ、サンカに自由を見るのか?」今井照容(もとサンカ研究会) ・「サンカたちとの短かい交流」清水おさむ(劇画家) ・「21世紀 民俗巷談」堤邦彦(国文学者) *まんが「木霊」勝又進 *まんが「丘の向こう」まどのかずや *論考「未来はノマド? 移動する人々の過去・現在・未来」長沼行太郎 *寄稿「サンカサークルを こうして立ち上げた」アラカワ(サークル代表) *講座「民俗学のABC」ノンバズル企画
-

お金信仰さようなら
¥1,980
版元:穴書 著:ヤマザキOKコンピュータ 四六判 並製(ビニールカバー) 224ページ 2026年1月刊 働いて働いて働いて働いて働いて、 収入を伸ばし、貯蓄を増やし、経済最優先の社会の中で、 成長と労働ばかりが求められてきた。 私たちは、「お金信仰の時代」に生まれ育った。 どれだけの資産があれば人は幸せになれるのか? 売れないものには価値がないのか? 経済成長すれば私たちの暮らしは豊かになるのか? 投資家やバンドマンとして、金融界のみならず国内外のパンク・シーンや多種多様な地下カルチャーを渡り歩いてきた著者が、 そこで培ってきた独自の視点でひとつひとつの疑問を解き、 貯蓄でもなく、選挙でもない、新しい選択肢を提示する。 『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』(6刷)で話題をさらった、 ヤマザキOKコンピュータの最新作。 今度こそ、くそつまらない未来は変えられる。 お金信仰が終わったあとの時代で、 何を指針に生きるのか? まだ名前の付いてない、新たな時代へと突き進む私たちのための入門書。
-

遥かな都
¥3,300
SOLD OUT
版元:作品社 著:池澤夏樹 四六判上製 304P 2026年1月刊 書物の中と博物館の遺物の間にしかない幻影の都市、アレクサンドリア。 その蜃気楼のような姿を追って遊歩する歴史紀行。 池澤訳、E・M・フォースター『ファロスとファリロン』を併録 《アレクサンドリア。紀元前三世紀にアフリカの地中海岸に造営されたこの都は二千数百年に亘って次々に支配する民族を替えながら繁栄し、一九五二年に至って本来の主人であるべきエジプト人の手に渡った。/それまでの間、文化的なものはすべて地中海の北岸からあるいは東のアラビア半島からやってきて、エジプト人はただ住民に穀物を供することだけを求められた。/だから、エジプト革命で都市の相貌はすっかり変わり、それ以前の姿は文学の中にしか残らなかった。華麗で壮大な、言葉だけで築かれた大厦高楼の集合。古代の詩人や思想家に始まって近代ギリシャ語の詩人K・P・カヴァフィス、イギリス人であるE・M・フォースターとロレンス・ダレルの作品群。/ぼくは若い時にこの文学の都市に出会って夢中になり、いくつかの文章を書き、翻訳もした。気がつけばこれが相当な量になる。そこでこれを一巻に纏めようと思い立った。》││本書「はじめに」より
-

低気圧の日、甘いミルクコーヒーの調べ
¥1,760
SOLD OUT
版元:KADOKAWA 著:onyoro 四六変形判 272ページ 2026年01月21日刊 揺らぐままのあなたのことを、世界は歓迎していますよ 「変わらない私も、変わってゆく私も、いつだって選べる。私は私の面影を残したまま、新しくなれるのだ。」 ☆ -------------------- ☆ 旅先の銭湯、 海辺でかじったクロワッサン、 ファミレスのおもちゃ売り場の指輪。 いつだって心の温度をあげてくれるのは ささやかだけど尊い、生活の手触りだ。 ☆ -------------------- ☆ あたたかなまなざしで綴られる、珠玉のイラストエッセイ集
-

北海道の生活史
¥4,950
版元:北海道新聞社 監修:岸政彦 編:北海道新聞社 A5判上製本 1280頁 2026年1月刊 「北海道の生活史」プロジェクトは、北海道の様々な人の人生を聞き取り、記録することを目的としてスタートしました。京都大学大学院文学研究科教授の岸政彦先生に監修いただき、聞き取りの手法も岸先生が編集した『東京の生活史』『大阪の生活史』(いずれも筑摩書房刊)、『沖縄の生活史』(みすず書房刊)のスタイルを取り入れました。 事務局の北海道新聞社は「身近な人の人生を書き残しませんか?」と、新聞紙面やネット上で「聞き手」を募集しました。応募者が多数いたため、岸先生と北海道新聞社は150人を決定するための選考会と抽選を行い、「聞き手」を決定しました。 その後、「聞き手」を対象に、取材する際の準備や心構え、聞き取りの進め方などを岸先生から教わる研修会を開催。語りの音源を文字に起こし、原稿にまとめる過程では「相談会」を複数回開催し、その都度、岸先生からの助言を受け、一次原稿を執筆しました。「聞き手」による編集作業、「語り手」による掲載内容の確認を経たうえで、修正を加え、それぞれ作品として仕上げました。 150本の作品は、このようなプロセスにより完成されたものです。
-

子どもでいられなかったわたしたちへ ヤングケアラー「その後」を生きる
¥2,090
版元:子どもの未来社 著:高岡里衣 四六判並製 246ページ 2025年11月刊 「わたしはずっと不思議だった。体の悪い家族がいないって、どんな感じなんだろう。自分のことだけ考えればいいって、どんな気持ちなんだろう。」 9歳の頃から難病の母の介護を担い、学業や仕事のかたわらで命を支える緊張と不安を抱え続けた著者。 24年にわたるケア生活が終わった後も、人生を再構築するための模索は続く。 元ヤングケアラー当事者が思いを込めて語る、過酷だが愛情に溢れたケア生活の真実。 【推薦コメント】 「ただ生きる」ことは、こんなにも難しい。だから、私たちは一緒に生きるのだと思う。 「強く生きなくてもいい、生きてさえいればいい」 子どもでいられなかった彼女は今、命を全肯定している。 ――土門蘭さん(文筆家、『死ぬまで生きる日記』ほか)
-

問いつめられたおじさんの答え
¥2,420
版元:石原書房 著:いがらしみきお 四六判 並製 144ページ 2026年1月刊 耳の聞こえないひとは、どうやって聞くの? どうしてみんな、携帯ばっかり見てるの? 家族って、なんですか? どうして嘘をついちゃいけないの? どうしてこんなに暑いの? 友だちって、必要? 勉強って、役に立つの? 人はどうして死んじゃうの? ――子供に訊かれたら困るその質問、おじさん=いがらしみきおが答えます。「webちくま」(筑摩書房)の人気エッセイ連載、待望の書籍化! 『ぼのぼの』『I【アイ】』の漫画家・いがらしみきおがまっすぐ、そしてユーモラスに綴る、素朴な疑問への答え。 東日本大震災とコロナ禍を経て、いがらしさんの世界との向き合い方がやさしく灯る、子どもにも大人にも面白い「人生の最初の問い」に寄り添う一冊。 各界の大人たちからの書き下ろし質問への回答を併録。
-

本を作るのも楽しいですが、売るのはもっと楽しいです。 韓国の文学を届ける
¥2,420
版元:岩波書店 著:金承福 四六判並製 212頁 2026年1月刊 出版社をおこし、書店をひらき、日本と韓国文学との架け橋として奔走する日々。読めば出版の未来が輝きだす、希望のエッセイ集。 大学の先輩が手書きで韓国語に訳してくれた吉本ばななの『キッチン』、茨木のり子の詩に重ねた民主主義への思い、ハン・ガンの初邦訳作品『菜食主義者』刊行の舞台裏――互いの国の物語をつないできた人々の情熱が、日韓文学の未来をひらく。出版社クオンの社長による、読むことへの愛と信頼に満ちたエッセイ!
-

マックスビル論考集
¥5,280
版元:みすず書房 著:マックス・ビル 編訳:向井周太郎・向井知子 A5判上製 344頁 2025年12月刊 ウルム造形大学の設計者・初代学長であり、永遠の定番ユンハンスの時計、ウルマー・ホッカーなどのデザインで知られる、スイスの建築家・芸術家・デザイナー、 マックス・ビル(1908–1994)。造形理論家、編集人として教育や出版活動にも情熱を注いだビルが残した芸術・デザイン・教育・建築に関する論考を、ビルと交流を重ねた向井周太郎・向井知子が精選し日本版オリジナル編集で一冊に。デザイン界、待望の書。
-

眠れない日にそっとめくる夜の図鑑
¥2,090
版元:三才ブックス 2,090円(税込) 監修 多田多恵子(植物監修)、小宮輝之(動物監修) A6変型上製本 240ページ 2025年12月19日刊 「小さな図鑑」シリーズ最新刊は、眠れぬ夜に寄り添う癒やしの図鑑。星空やオーロラなどの風景、天の岩戸やヘカテなど世界の神話、銀河鉄道の夜や千夜一夜物語などの物語、世界各地の夜の祭りや風習、夜に咲く花や光る生き物、夜を描いた絵画や音楽、そして詩や和歌に込められた言葉たち……。静寂や幻想、神秘があふれる夜の魅力を、美しい写真とともに紹介します。
-

人生の終わり方を考えよう 現役看護師が伝える老いと死のプロセス
¥1,760
SOLD OUT
版元:KADOKAWA 著:高島亜沙美 監修:西智弘 四六判並製 228ページ 2026年01月17日刊 死を見つめることは、生を考えること。 老いや死にも準備と努力が必要。 ・老いていく、そのプロセスとは? ・介護保険の仕組みと実情 ・終末期医療と緩和ケア ・死の事前準備と終活の話 ・自分らしい最期を迎えるためのポイント etc. 現役看護師だからこそ伝えられる、自分らしい最期の迎え方
-

松本清張の昭和
¥1,210
SOLD OUT
版元:講談社 著:酒井信 新書判 262ページ 2025年12月刊 想像を絶するほどの貧困、高等小学校卒、40歳を過ぎて文壇デビュー、そして国民作家へ。 逆境から運をつかみ取った生涯を描く、松本清張「初の本格評伝」が登場! 文豪が体現した「不屈のバイタリティ」と、それを育んだ「昭和という時代の力」を描く。 幼少期の秘話、思春期以後の恋愛、戦争体験……知られざるエピソードが満載。
-

酸いも、甘いも。 あの人がいた食卓 1977 - 2025
¥1,980
SOLD OUT
版元:オレンジページ 著 : 麻生要一郎 B6判並製 226ページ 2026年1月14日刊 料理家・麻生要一郎初の自伝&食エッセイ 食べることは生きることであり、人との思い出を作ること。食卓を中心に人生を振り返る、料理家・麻生要一郎初の自伝&食エッセイ。家業の継承放棄、両親との死別、高齢姉妹との養子縁組、新たな“家族”と囲む日々の食卓…酸いも甘いも、全ては人生の調味料。
-

フェイルセーフ
¥2,420
版元:KADOKAWA 著:吉田恭大 B6変形判 156ページ 2025年12月刊 短歌の本質を問い、歌集の概念を打ち砕く、最新短歌集が完成。 著者待望の第2歌集。 前作、『光と私語』(2019年)は、短歌界にとどまらず大きな話題となり、第54回造本装幀コンクール読者賞受賞、日本タイポグラフィ年鑑2020入選を達成。 現代における都市の浮遊感にいっそうの磨きをかけて書き綴る圧巻の歌群。
-

短歌の「てにをは」を読む
¥1,980
版元:いりの舎 著:大辻隆弘 四六判並製 212ページ 2025年3月刊 短歌における「てにをは」はこんなにも玄妙なのか――。 「てにをは」に注目して読むと、一首の歌は豊かに深く眼のまえに立ち現れてくる。 歌をゆたかに読むことは、歌を作ることよりもずっと楽しいことなのだ。 現代短歌きっての「読み巧者」である著者が、歌の魅力を鮮やかに語り尽くす! 「うた新聞」2020年4月号から2024年5月号まで50回に亘って連載され、好評を博したエッセイ、待望の単行本化。
-

なぜこの服は時代を超える定番なのか 一生モノの服の見極め方
¥1,980
SOLD OUT
版元:KADOKAWA 著:石川俊介 四六判並製 200ページ 2026年1月刊 「これでいい」ではなく、「これがいい」服を選びたい。カジュアルからモードまで、圧倒的に服を着倒してきたデザイナーが時代を超えて愛される68の「定番」を厳選。なぜこの価格なのか、なぜこの素材なのか、なぜ今もこの形なのか――。名品の裏側にある職人の技術やブランドの哲学をひも解き、「価格」ではなく「価値」で選ぶための視点を教えてくれる。流行に流されず、長く着られる一着を大切に楽しむための、自分にとっての「一生モノ」が見つかる一冊。
-

えーんえーんのうみ【サイン本予約 当店にて1/21日より原画展開催】
¥1,650
予約商品
当店にて2月1日トークイベント開催時にサインを描いてもらいその後発送となります。 著 近藤瞳(香川県在住) 子どもの気持ちにも、親の気持ちにも寄り添う絵本を。 『えーんえーんのうみ』(日本標準) 『おふとんからでたくない!』(ほんのハッピーセット えほん) 『まって!まって!』(ポプラ社) ・・・・・・・・・・・・ SBN(JAN) 9784820807698 出版社(メーカー名) 日本標準 本体価格(税抜) ¥1,500 発行日 2026/1/15 頁数 32 判型 A4変判
-

夜明けと音楽
¥2,200
SOLD OUT
版元:書肆侃侃房 著:イ・ジェニ 訳:橋本智保 四六変形並製 240ページ 2025年11月刊 「結局のところ物を書くというのは、よく知っている単語の中に、自分の悲しみを見つけること」 なくなったものの痕跡をたどり、孤独とともに創作する詩人イ・ジェニが綴るエッセイ集。 夜の闇に流れる、長く静かな時間に立ち上がる静謐な26編。 ある夜明けには涙のようにあふれる音楽について語り、またある夜明けには悲しみに満ちたプレイリストを思い出しながら詩を読む。 旅先で遭った不慮の事故、長いあいだ不眠症に悩まされたこと、ロックバンドで音楽に心酔していた二十代の頃のこと。 孤独とともに創作する詩人が、母の最期に立ち会い、イヨネスコやボードレールなど文人たちの足跡をたどり生まれた、詩と散文の境界を行き来するような言葉の記録。
-

怒っている子どもはほんとうは悲しい 「感情リテラシー」をはぐくむ
¥1,078
SOLD OUT
版元:光文社 著:渡辺弥生 新書判 296ページ 2026年1月刊 人生100年時代の現在、子どもたちに生じている心の危機。一因として「感情の理解の仕方や扱い方」を学ぶ機会に乏しい点がある。「自分の感情に気づく」「他者の気持ちを想像する」「気持ちを言葉で伝える」といった、感情に関する基礎的な力を育むことは、単に感情の安定をもたらすだけでなく、今の時代を生きる土台となる。世界でも注目のSEL(社会性と感情の学習)と感情リテラシーの育て方について第一人者が丁寧に解説。
-

アジア・トイレ紀行
¥2,200
SOLD OUT
版元:白水社 編著:山田七絵・内藤寛子 四六判並製 212ページ 2025年12月刊 トイレからアジアを覗く 私たちの生活のなかでも卑近なものと軽んじられがちな空間に、「用を足す」場としてのトイレがある。 しかし開発途上の国々や地域の文脈からすると、ことは違って見えてくる。トイレは、宗教や文化だけでなく公衆衛生、環境・エネルギー問題、ジェンダーや障害者の社会包摂といった社会的課題にかかわる、じつに奥の深いテーマなのだ。 日々調査に携わっている研究者たちは、現地のさまざまなトイレ事情に直面して苦労し、驚き、ときには恐怖を体験し、そして多くの発見をしている。本書で取り上げられるのは、日本をはじめ、東アジアに位置する韓国から東南アジア、南アジア、中央アジアを通って西アジアのトルコにまで至る、一九の国と地域だ。 トイレからアジアを覗くと何が見えてくるだろうか。 本書は、アジア研究に携わる総勢二〇名の専門家が急速に変わりゆく各地で遭遇した、トイレをめぐるカルチャー・ショックや現地社会に関するエピソードが満載のエッセイ集である。「いざ」というときに備えて、各エッセイの冒頭にはトイレに関する実用的な現地語講座がつけられているので、ぜひ活用していただきたい。
-

巨大建築はどうつくる? 日建設計をひもとく
¥2,860
SOLD OUT
版元:晶文社 編:五十嵐太郎+東北大学都市・建築理論研究室 A5判並製 328頁 2025年12月刊 東京スカイツリー、中野サンプラザ…… 有名巨大建築をてがける日建設計。 「都市を構築する見えない巨人」の 知られざる姿を明らかに! 都市はスター建築家だけがつくっているわけではない。多くの建物は、ゼネコン、組織設計が建てている。日建設計は世界でも最大規模の組織設計事務所であり、東京・渋谷や大阪・梅田の再開発、東京スカイツリー、中野サンプラザなど、誰もが知る巨大プロジェクトを数多く手がけてきた。 1000人を超える建築家が所属する日建設計には巨大組織ならではの強みと弱みがある。語られることのなかった「集団で設計する組織の全貌」を気鋭の建築家・建築史家が解き明かす! 【執筆陣】浅子佳英 磯達雄 一色智仁 菊地尊也 倉方俊輔 坂牛卓 菅野裕子 髙橋響 藤村龍至 吉野弘 李瀾昊(五十音順)