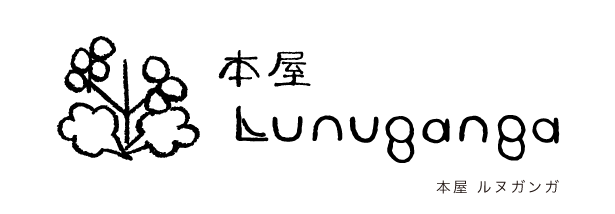-

まちに生きるローカル商店 14事例にみる生き残りかた
¥2,530
版元:ユウブックス 編著:URローカル商店研究会 四六変形判 228ページ 2026年1月刊 銭湯、駄菓子屋、豆腐屋、文具店…。まちに暮らす人々とともに生きながら、その“まち”らしい風景を生み出す“ローカル商店”は、まちの魅力をかたちづくるもの。 本書では経営危機を乗り越えた14軒のローカル店の復活ストーリーと生き残りの工夫をまとめた。各店の生き残り術を抽出したポイント、年表やデータも掲載。 まちづくり・事業承継に興味のある人に向けた、魅力的で持続可能なまちの実現を目指すための一冊。
-

お金信仰さようなら
¥1,980
版元:穴書 著:ヤマザキOKコンピュータ 四六判 並製(ビニールカバー) 224ページ 2026年1月刊 働いて働いて働いて働いて働いて、 収入を伸ばし、貯蓄を増やし、経済最優先の社会の中で、 成長と労働ばかりが求められてきた。 私たちは、「お金信仰の時代」に生まれ育った。 どれだけの資産があれば人は幸せになれるのか? 売れないものには価値がないのか? 経済成長すれば私たちの暮らしは豊かになるのか? 投資家やバンドマンとして、金融界のみならず国内外のパンク・シーンや多種多様な地下カルチャーを渡り歩いてきた著者が、 そこで培ってきた独自の視点でひとつひとつの疑問を解き、 貯蓄でもなく、選挙でもない、新しい選択肢を提示する。 『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』(6刷)で話題をさらった、 ヤマザキOKコンピュータの最新作。 今度こそ、くそつまらない未来は変えられる。 お金信仰が終わったあとの時代で、 何を指針に生きるのか? まだ名前の付いてない、新たな時代へと突き進む私たちのための入門書。
-

北海道の生活史
¥4,950
SOLD OUT
版元:北海道新聞社 監修:岸政彦 編:北海道新聞社 A5判上製本 1280頁 2026年1月刊 「北海道の生活史」プロジェクトは、北海道の様々な人の人生を聞き取り、記録することを目的としてスタートしました。京都大学大学院文学研究科教授の岸政彦先生に監修いただき、聞き取りの手法も岸先生が編集した『東京の生活史』『大阪の生活史』(いずれも筑摩書房刊)、『沖縄の生活史』(みすず書房刊)のスタイルを取り入れました。 事務局の北海道新聞社は「身近な人の人生を書き残しませんか?」と、新聞紙面やネット上で「聞き手」を募集しました。応募者が多数いたため、岸先生と北海道新聞社は150人を決定するための選考会と抽選を行い、「聞き手」を決定しました。 その後、「聞き手」を対象に、取材する際の準備や心構え、聞き取りの進め方などを岸先生から教わる研修会を開催。語りの音源を文字に起こし、原稿にまとめる過程では「相談会」を複数回開催し、その都度、岸先生からの助言を受け、一次原稿を執筆しました。「聞き手」による編集作業、「語り手」による掲載内容の確認を経たうえで、修正を加え、それぞれ作品として仕上げました。 150本の作品は、このようなプロセスにより完成されたものです。
-

問いつめられたおじさんの答え
¥2,420
版元:石原書房 著:いがらしみきお 四六判 並製 144ページ 2026年1月刊 耳の聞こえないひとは、どうやって聞くの? どうしてみんな、携帯ばっかり見てるの? 家族って、なんですか? どうして嘘をついちゃいけないの? どうしてこんなに暑いの? 友だちって、必要? 勉強って、役に立つの? 人はどうして死んじゃうの? ――子供に訊かれたら困るその質問、おじさん=いがらしみきおが答えます。「webちくま」(筑摩書房)の人気エッセイ連載、待望の書籍化! 『ぼのぼの』『I【アイ】』の漫画家・いがらしみきおがまっすぐ、そしてユーモラスに綴る、素朴な疑問への答え。 東日本大震災とコロナ禍を経て、いがらしさんの世界との向き合い方がやさしく灯る、子どもにも大人にも面白い「人生の最初の問い」に寄り添う一冊。 各界の大人たちからの書き下ろし質問への回答を併録。
-

松本清張の昭和
¥1,210
版元:講談社 著:酒井信 新書判 262ページ 2025年12月刊 想像を絶するほどの貧困、高等小学校卒、40歳を過ぎて文壇デビュー、そして国民作家へ。 逆境から運をつかみ取った生涯を描く、松本清張「初の本格評伝」が登場! 文豪が体現した「不屈のバイタリティ」と、それを育んだ「昭和という時代の力」を描く。 幼少期の秘話、思春期以後の恋愛、戦争体験……知られざるエピソードが満載。
-

わたしもナグネだから 韓国と日本のあいだで生きる人びと
¥2,090
版元:筑摩書房 著:伊東順子 四六判並製 256頁 2025年11月刊 韓国と世界のあいだの人生を聞きとる、他にはないノンフィクション アメリカに渡った武闘家マスター・リー、中国朝鮮族の映画監督チャン・リュル、日本で出版社を始めたキム・スンボクほか、韓国と世界の間の人生を聞き、描く。
-

「ソロ」という選択 自分だけの特別な人生を築く
¥3,080
版元:青土社 著:ピーター・マグロウ 四六判並製 320P 2025年11月刊 ひとりがダメだなんて誰が決めた! 社会は結婚を前提にできていて、独身者向けの本はいいパートナーを見つける方法ばかり……でも、それって本当に自分にとって必要なことなの? ソロ・プロジェクトを唱導する著者が、ひとりでいることの喜び、社会性、充実感、そして規則にしばられない最高に幸せな人生の送りかたを教えてくれる。そうだ、自分は自分のままでいいんだと勇気づけられる。ひとりの人も、パートナーがいる人も、ここから「ソロ」をはじめよう
-

小さな店をつくりたい 好きな仕事で生きる道
¥1,760
版元:家の光協会 著:井川直子 四六判並製 192ページ 2025.12刊 今の時代になぜ、「小さな店」だったのか。 彼らはなにも、新しい感覚の店をつくりたかったわけじゃない。 「自分にとって大切なこと」を自身に問いかけた結果である。 ―まえがきより抜粋― 店づくりに関わる取材に長く携わり、独自の視点で、「食」にまつわるノンフィクションを書き続けてきた著者が、10坪あまりの小さな飲食店を営む8人(組)を取材。「この店主にぜひ話を聞きたい」という熱い思いで、独立10年以内の8店を厳選しました。店を始めるまでの経緯や、店にかける思い、店づくりや経営の工夫などを掘り下げ、書き下ろした充実の内容。それは、いずれ独立して店を始めたい人だけでなく、仕事や生き方に悩む人、物づくり興味がある人にも響く内容です。
-

社内政治の科学 経営学の研究成果
¥2,200
版元:日本経済新聞出版 著:木村琢磨 256ページ 四六判並製 2025年11月17日刊 印象操作、派閥、権力争い、ゴマすり、社内人脈、根回し… 世界の学術研究に基づく「理論・フレームワーク」 経営学者が、研究成果に基づき「ビジネスパーソンに必要な政治力」を読み解く 【著者より】 社内政治の研究は世界的には主要な研究テーマのひとつであり、決して珍しいものではありません。私の専門は経営学の中の組織行動という、主に人材マネジメントを扱う分野です。 世界で広く読まれている組織行動の教科書には、多くの場合「権力と政治」という章が含まれています。これらの教科書は、一流学術誌に掲載された研究成果をもとに執筆されていて、「権力と政治」の章も豊富な先行研究に基づいて書かれています。 今日も世界中で多くの人が、ビジネススクールなどで社内政治を専門領域の一つとして学んでいます。 古典的な経営学では、組織は合理的に動くものとされてきました。しかし現実には、政治的なやりとりが会社の動きを左右する場面も多くあります。そのため、経営学も社内政治を前提にした議論を取り入れながら発展してきました。 本書で紹介した社内政治に関する知見や技術は、理論研究や実証研究に基づいたものであり、いずれも実務に直結する内容です。
-

ちゃぶ台 14 特集:お金、闇夜で元気にまわる
¥1,980
版元・編集:ミシマ社 四六判変形 158 ページ 2025年12月16日刊 日経株価が最高値になっても、物価高・米不足は起き、暮らしの経済は疲弊―― 生活者が生き生きする、別の「お金のまわり方」が、「闇夜」=ちいさな経済圏に広がっているのでは これを探るため、創刊10周年を迎えた今号はW特集を掲げます! 特集① お金、闇夜で元気にまわる ・書店と出版社が組み、限界を超えたイベント 「ちゃぶ台フェスティバル@ウィー東城店」徹底レポート! 目撃者・松村圭一郎(論考)「なんのための『経済』なのか?」 主催者・佐藤友則(インタビュー)「経営の発想の転換で本屋さんをくすぐっていく」 ・湯澤規子(随筆)「テーマの火は闇夜に灯る」 ・高橋久美子(エッセイ)「土の近くでまわる、お金のはなし」 ・土井善晴(随筆)「料理とお金」 ・平川克美(論考)「隠居ジジイの家計簿」 特集② 十年後の移住のすすめ ・本誌創刊号「移住のすすめ」を読み、本当に周防大島に移住した若者が寄稿 垂井綾乃「周防大島に吹く風に身を任せていたら」 ・移住先輩世代が周防大島の「今」を証言 内田健太郎(エッセイ)「鯖とヘソ娘」 中村明珍(コメント)「十年後の移住のすすめ」 ●巻頭漫画:益田ミリ「今日の人生 出張版」
-

仕事文脈 vol.27 売る、買う、悩む
¥1,320
版元:タバブックス A5判並製 128頁 2025年12月9日刊 特集1 売る、買う、悩む 億万長者だったらと妄想する お金なんか消えた社会を夢想する どちらでもない現在地から 買ったり、売ったり、買わなかったり 安いと助かるけどズルしたくない ほかの人のやり方も知りたい 悩み続ける「売る」と「買う」のいろいろ 消費的な消費と、投資的な消費 ヤマザキOKコンピュータ 倫理はトリミングすればいい 呉樹直己 イスラーム文化から私たちの損得勘定思考を見直す 長岡慎介 ちょっとマシなうちらの買い物 オーガニックショップから 暴力や搾取に関わらない買い物の輪づくり 赤塚瑠美さん 自分のお金が虐殺に使われたくない ボイコット商品の動画をInstagramで発信 カワナイさん アップルストア前でスタンディングデモ コンゴ戦争に無知なまま紛争鉱物を消費する私たち もずさん ヴィーガンとして「反搾取」を実践 社会に溶け込んだ構造や加害性に問いを持つ chiharuさん アンケート企画 売るとき、買うとき、これいらなくない? 何を買って、どう生きる? リアリティのある人生の設計図を考える 「みんなで生き残る」ためのインフラを 「独立出版者エキスポ」実行委員会インタビュー 特集2 ユーモア作戦 今って何が面白いんだろう? もう笑えないネタがある 笑い飛ばさないとやってられない現実がある 誰かの足を踏むかもしれない 誰かとつながるきっかけになるかも 傷つきにも、気づきにもなるから ユーモアの作戦を練る ユーモアクリエイティブ 奥田亜紀子 タイトル笑いを当事者の手に取り戻す。東海林毅監督に聞く、クィアなコメディ映画の作り方 ユーモアでレジスタンスする サミー・オベイドのスタンダップコメディ現場レポート アンケート企画 今、何見て笑ってる? 笑えなかったもの編集部座談会 ユーモアクリエイティブ momoboo ◎連載 文脈レビュー 漫画/講演/本/展覧会 文脈本屋さん TOUTEN BOOKSTORE 「聞く」という仕事 辻本力 40歳、韓国でオンマになりました 木下美絵 無職の父と、田舎の未来について。 さのかずや 虹色眼鏡 チサ 男には簡単な仕事 ニイマリコ 仕事文脈コラム
-

人生の「成功」について誰も語ってこなかったこと 仕事にすべてを奪われないために知っておきたい能力主義という社会の仕組み
¥1,705
版元:KADOKAWA 著:勅使川原真衣 四六変形判並製 272ページ 2025年11月刊 「成功者」って増えるの? 「公平な競争」は存在する? 「誰にでもできる仕事」なんてある? 「自分の人生は合っているのか?」――答えも納得も成長も、実はあなたが定義しなければならない。 能力主義をときほぐす今もっとも支持される組織開発専門家、最新刊 「本当にひとりひとりの生を大切にするのなら、「成功」が必要なのではなく、 成功や失敗なんて安直な二項対立ではなく、どんな人であれ、生存権が保障されていることではないだろうか。」(本文より)
-

肯定からあなたの物語は始まる 視点が変わるヒント
¥1,760
版元:講談社 著:稲葉俊郎 四六判並製 208ページ 2025年11月刊 「上司のひと言をさらっと聞き流せない」「ゆらいでしまう自分でなくなりたい」「気づけば自己否定の穴に落ち……」――。 著者の稲葉俊郎さんは、こうした状態なら「いのちの泉が枯れている」場合が多いといいます。 生きにくさや不安さえも豊かさに変えられるのが「いのちの力」です。いのちの力が強まったとき、悩みは成長の糧になります。 いのちの力を強めるためのウェルビーイング(個人も社会もよい状態)の活動を行っている稲葉さんは、西洋医学だけではなく伝統医療や心理学など幅広く修めてきた医師です。 「死んでからでは遅い。生きているうちに気づかなきゃ!」 横尾忠則氏(現代美術のレジェンド)が本書の必要性をこう述べています。 稲葉さんは、心の豊かさや人生哲学をテーマにしたテレビ番組や雑誌にも多く登場。 治療現場や旅先での出会い、温泉、演劇、アート、本などを通して、いのちという視座を自然に気づかせてくれるかけがえのない一冊です。
-

WORKSIGHT 29 アーカイブする?
¥1,980
版元:コクヨ株式会社 編:WORKSIGHT編集部 A5判変形 128ページ 2025.11.19刊 コクヨが制作中の「生活社史」を巡る岸政彦との対話、様々な企業による「仕事の蓄積、その方法と意味」、アーカイブ施設としての図書館の役割、「公共的な歴史と個人の記憶のあいだ」を揺れ動く複数のエッセイ、そしてブックリストまで。何を残すかではなく「なぜ残すのか」を問うことで、過去との向き合い方を改めて考える一冊です。
-

なぜ人は締め切りを守れないのか
¥1,980
版元:堀之内出版 著:難波優輝 288ページ 2025年11月刊 私たちは実のところ、「締め切り」のことをよく知らないまま生きている。 ときに私たちを苦め、ときに私たちを奮い立たせる「締め切り」とは何なのか? 「締め切り」から、現代社会に深く埋め込まれたルールを描き出し、豊かな生き方を探る哲学的冒険。 “我々は、いわば「時間的な無理」をさせられている。生きることの柔軟性をどう取り戻すか。この時間論には、哲学の新しい文体がある。すごく良い本だと思った。元気が出る本だ。” ──千葉雅也 時間について:時間とはそもそも何なのか? 計画について:昔の人はもっとのんびり生きていた 仕事について:無理な要求から逃れる方法は? 死 について:最大にして最後の締め切りを考える ●締め切りの間を縫って、私たちが〈いい時間〉を手に入れるために “残業によって得られる賃金は計算できる。さまざまな締め切りの集合体である「プロジェクト」は、時間を対価に成果を提示する。いっぽうで、愛する人と過ごす時間、趣味に没頭する時間の価値は計算が難しい。私たちは、〈いい時間〉を計量することができずにいるのだ──。”
-

感情労働の未来 脳はなぜ他者の”見えない心”を推しはかるのか?
¥2,090
版元:河出書房新社 著:恩蔵絢子 四六判並製 244ページ 2025年10月刊 AI時代、人間が持つ最大の能力は、感情になる! 感情を抑圧し“他者にあわせる“ストレスフルな現代から、“他者を理解する“感情的知性の未来へ。人間の可能性に話題の脳科学者が迫る。
-

「休むと迷惑」という呪縛 学校は休み方を教えない
¥1,210
版元:平凡社 著:保坂亨 新書判 256ページ 2025年10月刊 なぜ仕事は休みにくいのか? 学校教育のあり方を出発点に、理不尽を我慢することに慣れた社会を「休みやすく」する方法を考える。 働き方改革が推進され、コロナ禍を経た今もなお、長時間労働はなくならず、その対策も後手に回り続けている。過労死、「自己研鑽」という労働時間のグレーゾーン、そして「定額働かせ放題」と言われる教員の働き方……。 なぜ私たちは「休むこと」をためらってしまうのか? その原因は学校教育にあった。 皆勤賞で「休まないのは良いこと」という意識を刷り込まれ、部活動を通し「休むと皆に迷惑がかかる」と考えるようになる――。 本書では、戦後の学校教育が教えてきた「休まない美徳」の問題点を指摘しつつ、誰もが休みやすい社会を作っていくためのヒントを示す。
-

すぐ役に立つものはすぐ役に立たなくなる
¥1,980
版元:プレジデント社 著:荒俣宏 四六判並製 328ページ 2025年3月刊 「無理」「無茶」「無駄」が人生を面白くする。 一日12時間、風呂、トイレの中でも書物を貪り読み続け、 辿り着いた「得るためには何かをあきらめる境地」とは──?
-

お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点
¥1,650
版元:朝日新聞出版 著:田内学 四六判並製 256ページ 2025年10月7日刊 「お金さえあれば不安は消える」─そんな幻想に、私たちはいつからとらわれてしまったのか。人口減少、物価高、老後資金……先の見えない時代で必要なのは、不安の正体を見きわめ、社会と向き合う視点だ。ともに生き延びるための生存戦略を描こう。
-

ルポ失踪 逃げた人間はどのような人生を送っているのか?
¥1,485
SOLD OUT
版元:星海社 著:松本祐貴 新書判 192ページ 2025年9月刊 失踪の赤裸々な事情を経験者たちが大いに語る! 失踪―それは現在の人間関係や社会的立場を捨て、新たな環境で別の人間として生き直すことである。一見するとわれわれの日常から縁遠いように思われる失踪だが、現在日本の行方不明者は年間9万人、およそ1000人に1人にのぼる。本書はそんな近くて遠い存在である行方不明者や残された人々に取材し、失踪の理由から実行の手順、現在の生活までの一部始終を記した本である。失踪者はいかに生き、何を考えているのか? 人生がつらい、逃げたいと思ったことが一度でもある人に捧げる、失踪のリアルを通じて生きづらさと向き合う術を考え直す新しい人生論にして幸福論。
-

ホームレス文化
¥2,640
版元:キュートット出版 著:小川てつオ 四六判並製 382ページ 2025年9月3日刊 都会の公園の一角、ホームレスの集住地。20年前、そのコミュニティの豊かさに衝撃を受け、自らもテントを建てて暮らし始めた小川てつオ。 以来、排除の圧力や社会の変化をくぐり抜け、隣人たちと織りなす生活をブログ「ホームレス文化」で発信し続けてきました。本書はブログより記事を厳選・再構成し、テント村20年の生活史として世に送るものです。 差別や暴力の標的、一方で支援の対象とだけ見なされるホームレスという存在。しかし、ここには生活があり、「見えない豊かさ」がある! 「存在そのもの」で生きる魅力的な隣人たちとの日常や支え合う知恵が、いきいきとした筆致で描き出されます。公共地に暮らすことで見えてくる、この社会の本質もあぶり出されていく。本書はテント村の物語であると同時に、ホームレスの「地点」から紡ぐ、生きた思想の書でもあるのです。
-

老いのレッスン
¥1,760
SOLD OUT
版元:大和書房 著:内田樹 四六変並製 208ページ 2025年9月刊 人生に必要なのは「どんな人と結婚しても、そこそこ幸せになれる能力」。思い通りにいかない人生を、機嫌よく生きるための知恵と術。
-

老いと暮らすヒント
¥1,870
版元:Haza 著:西川勝 四六判並製 160ページ 2025年7月刊 「認知症の人にはさまざまな問題があり苦しいことがある、ということはもちろん知ってほしいと思います。けれども、その中で生きる人の姿を伝えることで、みなさんに「ああ、認知症の人はそんなすごいことをしているんだ。ファンになってみようかな」という気持ちになってもらえれば、と期待しています」 認知症の人たちが懸命に生きる姿から、どれほどの豊かさを私たちは受け取ることができるか――。 看護の現場から臨床哲学へと歩んできた著者が、専門家ではない「ふつうの人」だからこそできるケアについて語り、認知症の人のファンになってほしいと呼びかける。今・ここにある「老い」と真剣に向き合い、丁寧に付き合っていくためのヒント。発達心理学者・麻生武との対談や「家庭介護のポイント 実践編」も収録。寄稿 青山ゆみこ
-

うどん以上のことはできません
¥1,760
版元:イマジカインフォス 著:三好修 四六判並製 208P 2025年7月刊 香川県坂出市で三代続く「日の出製麺所」。製麺を本業としているためうどんを提供するのは、平日の11時半から12時半のわずか1時間ですが、その時間をねらって、全国から熱烈なファンがかけつけ大行列ができます。三代目の当主・三好修氏が目指しているのは、「何もつけなくてもおいしい麺」。天候や湿度に合わせて小麦粉をブレンドし、その日その時に一番いい状態の麺を打つ。店で提供するのは「あつい」「冷たい」「ぬるい」「釜玉」の4種類のみですが、そのシンプルな一杯に、遠方から足を運ぶ人が後を絶ちません。「自分は、うどん以上のことはできません」と語る三好氏。飾らず、迷わず、まっすぐに麺と向き合う。うどん好きがうなるひと玉はどうやって生まれるのか。知られざる製麺所の舞台裏を記録したドキュメンタリー・ノンフィクション。