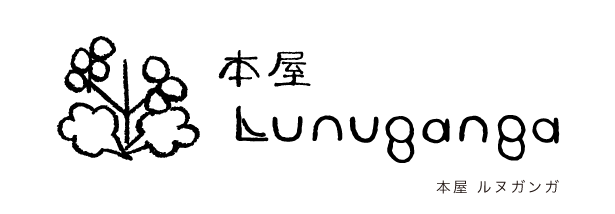-

デッドエンドで宝探し
¥2,200
版元:hayaoki books 著:能町みね子 ブックデザイン:小磯竜也 A5判並製 156ページ 2026年1月刊 青森県庁が運営するWEBメディア「まるごと青森」で不定期連載中の「あんたは青森のいいとこばかり見ている」がまさかの書籍化! 公開されるたびに県境を飛び越えて大バズりしたあの記事やこの記事も収録。 本州のデッドエンド・青森を、隅々まで(というか主に隅々だけを)散策し、著者にとっての宝物のようなできごと(?)を書いた、重箱の隅的冒険エッセイ。 能町みね子ならではの視点と軽快な筆致で綴られた面白エピソードと写真多数で、青森に全く関係ない人もしっかり楽しめる一冊です。
-

【サイン本】ずっとあった店 BARレモン・ハート編
¥1,540
版元:ことさら出版 著:スズキナオ フルカラー単行本 B6判並製 82ページ 2025年12月刊 ことさら出版とスズキナオさんは、昨年から『ずっとあった店』という書名で刊行予定の単行本の制作を進めています。『ずっとあった店 BARレモン・ハート編』は、その『ずっとあった店』のフルカラー分冊版で、北海道札幌市のバー「BARレモン・ハート」をスズキさんが取材した2日間の記録です。
-

本当の登山の話をしよう
¥2,090
版元:deco 著:服部文祥 B6判並製 240P 2026/02刊 人はなぜ山に登るのか――著者30年にわたる「登山批評」の集大成。 第Ⅰ部は、デビュー作『サバイバル登山家』以前に書かれた、著者の原点ともいうべき隠れた名篇のほか、若き日に憧れた和田城志へのインタビュー、山で書いた「遺書」についての回想記を収める。 第Ⅱ部は、山野井泰史、星野道夫、フリチョフ・ナンセン、デルスー・ウザーラ、ウォルター・ウェストンら、著者が敬愛する人物たちを通して登山とは何かに迫る。また、クマとのつきあい方、世界と日本の最高所の意義について私論を展開する。 第Ⅲ部は、廃山村での自給自足のほか、狩猟のパートナー・ナツ(犬)の失踪騒動、もうひとつのライフワーク・中距離走の喜びなど、近年の暮らしのあれこれを語る。最後に、登山よりも先に志したという文章表現について論じる。 〈なぜ山に登るのかという質問を、山に登らない多くの人が、山に登る人に投げかける。 わかりやすく答えるのは難しい。質問に含まれる「なぜ」の裏には、「辛くて、大変で、無償なうえに、もしかしたら死ぬかもしれないのに、なぜ」という思いが隠されているからだ。「死ぬかもしれないのになぜ」とまっすぐ聞いてくれるなら、風景やストレス発散が、登山の理由にならないことは明白だ。景色を見るために死ぬ思いをする人はあまりいない。 山に登る理由はただ一つ、自己表現だと、思っている。自分が山(ひいては地球というフィールド)で何ができるのか。それを知りたいし、示したい。そういう意味では芸術一般と変わりがない。登山はダンスに似た身体表現の一種類だと私は考える。〉「富士山 世界で一番手頃な高所」より
-

ポルトガル限界集落日記
¥1,870
SOLD OUT
版元:集英社 著:浅井晶子 四六判並製 208ページ 2026年1月26日刊 隣の家は山向かい。人口10人。言語、文化、人種、完全アウェーのスローライフ! 大都市ベルリンからポルトガルの限界集落に夫婦で引っ越した、ドイツ語翻訳者の浅井さん。山奥の一軒家、憧れのスローライフはシビアな現実のはじまりで!? 納豆の自作、修繕しながら暮らす家、オリーブオイルとワインの共同制作――。 ヨーロッパの片隅から、移民夫婦の異文化生活と世界へのまなざしをお届けします。 【著者プロフィール】 浅井晶子 (あさい・しょうこ) ドイツ語圏文学翻訳者。1973年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程単位認定退学。2003年トーマス・ブルスィヒ『太陽通り ゾンネンアレー』でマックス・ダウテンダイ翻訳賞、2021年ジェニー・エルペンベック『行く、行った、行ってしまった』で日本翻訳家協会賞〈翻訳特別賞〉受賞。訳書にイリヤ・トロヤノフ『世界収集家』、トーマス・マン『トニオ・クレーガー』、エマヌエル・ベルクマン『トリック』、ローベルト・ゼーターラー『ある一生』、ユーディト・W・タシュラー『国語教師』『誕生日パーティー』、ユーリ・ツェー『メトーデ 健康監視国家』ほか多数。 2021年からポルトガルの限界集落S村に暮らしている。
-

おさまる家 井田千秋作品集
¥2,750
版元:実業之日本社 著:井田千秋 B5判変型 192ページ 2026年01月22日刊 この家に、帰りたい。」 空想に浸る。本を読む。食べる。眠る。 ただ、なんとなくそこに居る。 するりとおさまる。 ここは、たいへん居心地の良い とっておきの場所。 同人作品7本に加え、描きおろし漫画やエッセイまでたっぷり収録! 『家が好きな人』井田千秋のすべてが詰まった初の作品集。
-

東欧センチメンタル・トリップ
¥2,090
版元:草思社 著:イスクラ 四六判並製 240ページ 2025年12月刊 「旅に出たい。でも今すぐは難しい…」「東欧に行ってみたい。でもちょっと敷居が高くて……」―そんな方におすすめしたいフォトエッセイです。 ワルシャワ、プラハ、モスクワ——。子どもの頃、図鑑で見たぼんやりした写真の向こうにあった“鉄のカーテン”の世界。なんだか謎めいている…でも、強く惹かれてしまう。著者はそんな憧れをずっと抱えたまま、民主化直後の90年代、20歳のときに短期留学のサマーコースでドイツ東部を選び、単身で旅立ちました。 旅はやがて「その土地が抱えてきた時間を感じる」方向へと変わり、長い時間をかけて続いていきます。懐かしさと発見が交錯するページをめくるたび、自然と心が東へ向かうような旅情が広がっていきます。 この本の魅力をひとことで言うなら、「記憶が濃い」こと。旅先で出会った人の笑顔や親切。食堂や鉄道の旅で供される料理や家庭料理のあたたかさ。“記録”というより、“体の中に染み込んだ記憶”が、丁寧に掘り起こされたエッセイとなっています。 旅先で出合った料理を再現した文字レシピも収録しており、読むだけでなく“味わう旅”ができることも大きな魅力です。著者の撮影による巻頭カラーページの美しい写真も要必見。東欧を愛する方はもちろん、これから東欧を知る方にとっても、新たな扉を開いてくれる1冊になることでしょう。
-

まちに生きるローカル商店 14事例にみる生き残りかた
¥2,530
版元:ユウブックス 編著:URローカル商店研究会 四六変形判 228ページ 2026年1月刊 銭湯、駄菓子屋、豆腐屋、文具店…。まちに暮らす人々とともに生きながら、その“まち”らしい風景を生み出す“ローカル商店”は、まちの魅力をかたちづくるもの。 本書では経営危機を乗り越えた14軒のローカル店の復活ストーリーと生き残りの工夫をまとめた。各店の生き残り術を抽出したポイント、年表やデータも掲載。 まちづくり・事業承継に興味のある人に向けた、魅力的で持続可能なまちの実現を目指すための一冊。
-

アジア・トイレ紀行
¥2,200
版元:白水社 編著:山田七絵・内藤寛子 四六判並製 212ページ 2025年12月刊 トイレからアジアを覗く 私たちの生活のなかでも卑近なものと軽んじられがちな空間に、「用を足す」場としてのトイレがある。 しかし開発途上の国々や地域の文脈からすると、ことは違って見えてくる。トイレは、宗教や文化だけでなく公衆衛生、環境・エネルギー問題、ジェンダーや障害者の社会包摂といった社会的課題にかかわる、じつに奥の深いテーマなのだ。 日々調査に携わっている研究者たちは、現地のさまざまなトイレ事情に直面して苦労し、驚き、ときには恐怖を体験し、そして多くの発見をしている。本書で取り上げられるのは、日本をはじめ、東アジアに位置する韓国から東南アジア、南アジア、中央アジアを通って西アジアのトルコにまで至る、一九の国と地域だ。 トイレからアジアを覗くと何が見えてくるだろうか。 本書は、アジア研究に携わる総勢二〇名の専門家が急速に変わりゆく各地で遭遇した、トイレをめぐるカルチャー・ショックや現地社会に関するエピソードが満載のエッセイ集である。「いざ」というときに備えて、各エッセイの冒頭にはトイレに関する実用的な現地語講座がつけられているので、ぜひ活用していただきたい。
-

山の時刻
¥2,178
版元:PIE International 文:小林百合子 写真:野川かさね A5判変型並製 224ページ 2025年12月刊 山や自然が刻むリズム、そこに流れる時間に身をゆだねると、たいていのことは、きっとなんとかなると思えてくる。 一瞬で過ぎ去ってしまう、儚く美しい山の情景。それに目を凝らし、撮影を続ける写真家・野川かさねが撮り溜めてきた膨大な写真の中から珠玉の作品を厳選。それらからインスピレーションを得て生まれた四季折々、山にまつわる120の言葉と散文を収録し、「山に流れる時間」を刻んだビジュアルエッセイ。山での一瞬を焼き付けた129 枚の写真と、120点の言葉。それらは瞬間であり、点であり、時刻である。そのすべてをつなぎ合わせた時、ひと筋の「山の時間」が生まれる。「街の時間」とは異なる、おおらかで美しい流れに身をゆだねた時、これまで気づかなかった、ささやかでも大切なものが見えてくる。
-

MIDNIGHT PIZZA CLUB 1st BLAZE LANGTANG VALLEY
¥2,750
版元:講談社 著:上出遼平・仲野太賀・阿部裕介 四六変型並製 320ページ 2024年12月刊 目的なんて後付けでいい。 ただ胸が躍って、気づけばここまできていた。 降り立ったのはネパール、挑んだのは「世界一美しい谷」。 俳優・仲野太賀を被写体に、写真家・阿部裕介が撮り、TVディレクター・上出遼平が綴る! 見て、読んで追体験するクレイジーなトラベル・レコード、ここに爆誕!! 「ミッドナイト・ピッツァ・クラブ(MPC)」 ――真冬のニューヨークで天啓がごとく授かった名に導かれるようにして旅立った3人。ネパールはランタン谷を歩く一週間がはじまった。カトマンズを爆走する四輪駆動車、激痛を生む毒の葉、標高2440mにあるホットシャワー、地震で一度壊滅した村で韻を踏み続ける青年、ヒマラヤの甘露「アップルモモ」、回転するマニ車、見え隠れする陰謀の影(!?)数々の危機を乗り越え、出会いと別れを繰り返した先、3人を待ち受けていた光景とは――? これは、食って歩いて歌って寝て、泣いて笑って怒り狂う男たちの、汗と泥と愛にまみれた旅物語。
-

アゲハ蝶の白地図
¥1,540
版元:山と渓谷社 著:五十嵐邁 文庫判 424頁 2025.10刊 吸血ヒルの襲撃、飛行機の墜落、砂漠の熱波、そして原因不明の高熱。 未知のチョウを探し求めてどこまでも… 超破天荒!!な探検記 藤井一至氏(『大地の五億年』著者)イチ推し! 「幻の蝶を追い求めた会社員の命がけのクレイジージャーニー。夢中になるものが見つかれば、人生が楽しくなる。」
-

日本で一番美しい県は岩手県である
¥1,980
版元:柏書房 著:三浦英之 四六判並製 208ページ 2025/12/16刊 岩手在住・開高健賞受賞のルポライターが、独自の文化や信仰、暮らしといった「普段着の岩手」を切り取る日本再発見ルポエッセイ。 「この雪はどこをえらばうにもあんまりどこもまつしろなのだ」――宮沢賢治「永訣の朝」 ニューヨーク・タイムズが「行くべき52カ所」に選んだ盛岡、 神と人がともに生きる風土、 震災を経て歩み続ける人びと―― 今最も注目されるルポライターが、賢治が桃源郷「イーハトーブ」と呼んだ100年後の岩手を旅する。 「賢治はこの地を「イーハトーブ(ドリームランド)」と呼んだ。啄木は岩手山を見て「言ふことなし」と綴った。この本を読み終えたとき、あなたもきっとこう口にするはずだ。日本で一番美しい都道府県は、そう、岩手県である、と」――本書「はじめに」より
-

世界浴場見聞録
¥2,420
SOLD OUT
版元:学芸出版社 著:こばやしあやな 四六判 240頁(カラー 64頁) 2025年12月刊 50カ国を巡ったサウナ文化研究家の入浴記 浴場は、風呂やサウナだけにあらず。ロシアの灼熱浴室に身悶えながらも通い詰め、スリランカで温浴医療を求めて入院を志願し、モロッコの公衆浴場でムスリムと身を寄せ合って垢をすり、メキシコで蒸気浴部屋を司る古代の神々と邂逅する…身一つで世界50カ国を巡り歩いたフィンランド在住サウナ文化研究家の体当たり入浴旅
-

住む権利とマイノリティ 住まいの不平等を考える
¥3,080
版元:青弓社 編:青弓社編集部 四六判並製 228ページ 2025年12月刊 執筆者:金井 聡/杉野衣代/大澤優真/志村敬親/岡部 茜/植野ルナ/永井悠大/龔軼群 DV被害者や外国籍者、中・高年単身女性ほかマイノリティに焦点を当て、住まいをめぐる現況と課題を詳述する。さらに、支援に取り組むNPOと企業が改善策を提示する。住まいの問題を多角的に捉え、住まいの権利をマイノリティの視点から照射する。 都市部でのマンション価格や家賃の高騰が報じられる一方、部屋を借りることが難しい人たちの存在が可視化され、住まいをめぐる格差の問題は近年ますます注目を集めている。2020年に新型コロナウイルス感染症が感染拡大した際には、ホームレスやネットカフェ難民の問題など、住まいの格差が顕在化した。 現在の日本では、住む権利/住まいの権利が全員に保障されているとはいいがたい。入居を断られる、シェルターに入れない、入ったとしても環境が悪く落ち着いて暮らせない。「住宅弱者」「住宅確保要配慮者」などの言葉が広まり、住宅を確保するための法整備が進んできているが、安定した住まいから排除され不安定な生活を余儀なくされる人たちも存在している。 本書は、DV被害者や外国籍者ほかマイノリティに焦点を当て、住まいをめぐる現況と課題を詳述する。さらに、ホームレス支援に取り組むNPOと、住まい探しの状況改善に取り組む企業が、それぞれの視点から改善策を提示する。最も身近な「住まい」の問題を多角的に捉え、住まいの権利をマイノリティの視点から照射する。
-

脱力、台湾式。
¥1,760
SOLD OUT
版元:KADOKAWA 著:青木由香 四六判並製 256ページ 2026年1月刊 日本人よ、疲れたらこの島に逃げてきなさい! 台湾の出版社から出した『奇怪ねー 一個日本女生眼中的台湾』が台湾でベストセラーに。人気コーディネーター・青木由香さんの最新エッセイ。 台湾に暮らして約24年。最初はマッサージに魅せられ、次はお茶に取りつかれ、次第に台湾の人々に夢中に。24年の間に、台湾で結婚式を行い、台湾で出産、子育て、お店のオープン、会社設立と、何から何まで体験した青木由香さん。台湾に暮らし、台湾人の考え方に慣れると、日本に比べてとても合理的で生きやすいことに気が付いたそうです。 本書はそんな青木さんが24年間で経験したことを軸に、台湾人のやさしさや賢さの秘密がわかる1冊。 もちろんコーディネーター青木さんとして、台湾で訪ねてほしいエリアについても触れています。台湾旅行のお供にも、再度行きたくなった人にもおすすめです。
-

昭和界隈 写真でタイムトラベル
¥2,200
版元:朝日新聞出版 協力:朝日新聞フォトアーカイブ B5判並製 224ページ 2025年11月20日刊 「昭和100年」に写真で振り返る 人々の暮らしと時代の熱気。 人間くささ、暮らしのあたたかさが匂ってくる。 (映画監督 山田洋次) 朝日新聞の人気連載「朝日新聞写真館」をもとに再構成。 朝日新聞や「週刊朝日」「アサヒグラフ」などの雑誌に掲載された 報道写真のアーカイブより、昭和の人々の暮らしや社会風俗、 時代の熱量に満ちた写真を選りすぐり、ご紹介します。
-

きもの、どう着てる? 私の「スタイル」探訪記
¥2,200
版元:プレジデント社 著:山内マリコ A5判 176頁 2025年10月刊 着物の季刊誌『七緒(ななお)』の人気連載が、ついに書籍化! スタイルある20人の着物好きに、作家の山内マリコさんがインタビュー。 自らを「着物迷子」と語る山内さんが、それぞれの着方・生き方から 見えてきた「らしい」スタイルについてエッセイで綴ります。 着こなしのスパイスとなる小物紹介や、 お手入れお直しといった着物との付き合い方のヒントも満載。 スタイルを探訪するうちに「着たい」気持ちもムズムズと刺激される。 私らしい着物選びの指針となるような、何度でも立ち帰りたくなる一冊です。
-

最後の山
¥2,420
SOLD OUT
版元:新潮社 著:石川直樹 四六判変型 272ページ 2025年9月刊 23歳でエベレストを登頂して以来20年余。世界で最も高く危険な山々への挑戦はついに「最後の山」シシャパンマへ。人間を拒む「デスゾーン」でぼくが見たのは、偉大で過酷な自然の力と、我々はなぜ山に登るのかという問いへの答えだった──中判カメラを携え、人類の限界を超えようとする仲間たちと共に登った生の軌跡。
-

小説のように家を建てる
¥1,760
版元:光文社 著:吉川トリコ 四六判並製 220ページ 2025年10月刊 どこか遠くへ行きたかった。そうして、どういうわけだか、家を建てることになった。 土地を購入して家を建てることは、自分を縫いつけるようなことだと思っていた。今の日本で家を建てることなどリスクでしかないと。 住宅ローンにがんじがらめになり、どこへも行けなくなってしまうくらいなら、一生仮住まいでかまわない。死ぬまで無責任にちゃらんぽらんに自由に生きていたかった。 だから今、こんなことになってしまって驚いている。あの夢見がちなぼんくらがいっぱしの大人になって……。 家を建てるにあたってさまざまな本を読んだが、もう少し情緒的な、心の動きに寄り添ったエッセイのようなものを読んでみたかった。 ならば、自分で書いてみよう。どのような経緯で家を建てることになり、どのような観点で選択を重ね、どのような家を建てたのか。 物件を探しはじめ、新居の引き渡しにいたるまでの大冒険の記録を。
-

駅から徒歩138億年
¥1,980
版元:産業編集センター 著:岡田悠 四六判並製 364ページ 2025年10月刊 ウェブ記事累計1300万PVを超えるライター岡田悠の最新作は、 多摩川を河口から源流まで散歩した道程と思考の記録「川歩記」と、 果てなき好奇心が場所と時間を飛び越えていく不思議でやさしい10編の日常旅エッセイ。 全長138kmの多摩川を少しずつ歩きながら、これまでの旅を思い出す。 古いカーナビの案内で歩いたり、17年前に2秒見えた海を探したり、学生時代に住んでいた寮に泊まったり—— それは、空間の移動と時間の移動を組み合わせることによって生まれる、「自分だけの旅」だった。
-

柚木沙弥郎 旅の手帖 布にめざめたインドの旅
¥3,080
版元:平凡社 著:柚木沙弥郎 B6変形上製 240ページ 2025年10月刊 染色家として大きな転機となったインドの旅。鋭い観察眼と豊かな感性で異国の文化を捉えた旅の記録の第2弾。
-

装いの翼 おしゃれと表現と
¥2,640
版元:岩波書店 著:行司千絵 四六判上製 278頁 2025/09刊 多感な年頃を戦時下に生き、戦後、新たな創造の世界へと羽ばたいた三人の表現者――絵本画家・いわさきちひろ、詩人・茨木のり子、美術作家・岡上淑子。彼女たちは日々の装いを大切にし、暮らしの中でも美を愛おしんだ。袖を通したものに触れ、ゆかりのひとに逢い、時代背景をひもとく。丹念な取材から浮かび上がる、服と人生の物語。
-

コレクターズパレード 100人の収集生活
¥2,200
版元:小鳥書房 編:落合加依子・佐藤友理 B6並製 240頁オールカラー 2025年10月刊 ひとり暮らし100人の生活を綴ったエッセイ集 『ワンルームワンダーランド』に続く待望のシリーズ第2弾! 2歳の男の子から大学生、主婦、会社員、本屋の店主、音楽家、DJ、茶道家、公認会計士、カウンセラーなど、年齢も職業も住む場所もさまざまな100人に「なにか集めているものはありますか?」と尋ねるところからスタート。 「つい集めてしまう」 「なぜか捨てられない」 「自然と集まっていた」 と、それぞれが好きなものをささやかに集めて暮らす、収集生活の楽しさや苦悩。 人知れず集めたコレクションと、それが置かれた部屋の写真をエッセイとともに収録しました。 ページをめくるたびにコレクションたちが次々と姿を現し、個性を纏って歩みを進めていく。 色も形も背景も異なるものたちが連なってゆく光景は、まるでパレードのよう。 「捨てられなくて溜まっていくもの」から「夢を引き継ぐもの」まで、 100人の暮らしに散りばめられた小さな「心のときめき」が、このパレードを彩ります。 「なんかいい」と感じるものたちによって、日々がちょっと豊かになる。 本書は、誰かの瞳を輝かせるものや、誰にも気づかれない日常の断片をすくいあげるコレクションを通して、“好き”に触れるよろこびと、自分を大切に思う感覚を呼び覚まします。 あなたのそばにある、「なんでもないけど、なんでもなくない」ものたち。 その存在もまた、ひそやかなコレクションなのかもしれません。
-

海のまちに暮らす
¥2,200
SOLD OUT
版元:真鶴出版 著:のもとしゅうへい B6並製 140ページ 2025年7月刊 イラスト、デザイン、詩、小説をはじめ、最近では漫画まで。 ときには自身で製本し、出版、営業までをも行う弱冠25歳の作家・のもとしゅうへい。 コロナ禍であった2022年、のもとくんは大学を休学し、東京を離れて真鶴に移り住み、町の図書館でバイトし、真鶴出版でインターンをし、畑を耕しながら制作活動を行っていました。 都市を離れ、真鶴という港町で、土を触りながら感じた、日々の些細な生活の記録がさまざまな視点から描かれています。 第2版は、初版のその後の暮らしを描いたエッセイ三編を追加。 真鶴から鎌倉へと拠点を移した、今現在の暮らしから言葉が掬い取られています。 表紙の紙やインクの種類、表紙のイラストまで(!)も変化を加えています。 今後、増刷の度に今の暮らしの記録が継ぎ足されていく、「秘伝のタレ」形式のこれまでにない本です。 それぞれのエッセイには、描き下ろしの4コマ漫画や挿絵が付いています。 装丁ものもとくん自身によるもの。 誰しもの生活を、やさしく肯定してくれるような一冊です。