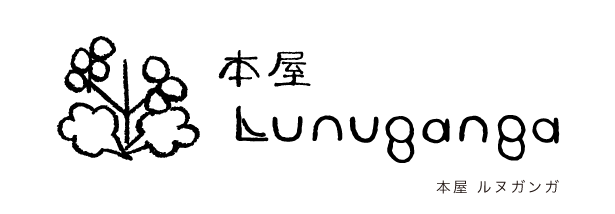-

批判的日常美学について 来たるべき「ふつうの暮らし」を求めて
¥1,980
版元:晶文社 著:難波優輝 四六判並製 256頁 2026年2月刊 現代は「ちゃんとする時代」。「ちゃんと働く」「ちゃんとした格好をする」……私たちはいつのまにか、ちゃんとすることを当然視し、それができない自分を責めながら生きている。だが、本当にちゃんとしなければならないのだろうか。 社会が要請する「ちゃんとしなければならない」に対して、自分の理由で反抗し、受け流し、交渉するための「道具」を追求すること。それが「批判的日常美学」の試み。 生活にまつわる様々なアイテム──料理、労働、ファッション、清潔感、コミュニケーション、性愛──などを題材に、「丁寧な暮らし」の呪縛から逃れ、いまだ到来しない「ふつうの暮らし」を模索する哲学的考察。他人と世界と自分をより自由に愛せるようになるためのメソッド。
-

返さない借り つながる贈与 資本主義を克服する、新しい共同性
¥2,090
版元:朝日新聞出版 著:岩野卓司 四六判並製 248ページ 2026年2月刊 資本主義を支える「借りを返す」原理を問い直し、返礼に回収されない「贈与の連鎖」の可能性を探る。災害時の相互扶助や「恩送り」的なコミュニティーの実践、さらに、デヴィッド・グレーバーらの思想を手がかりに、共同性の新しいかたちを描き出す。
-

どうすればよかったか?
¥1,650
SOLD OUT
版元:文藝春秋 著:藤野知明 四六判並製 192ページ 2026年01月刊 我が家の25年は〝失敗例〟です。 医学部に通うほど優秀だったが、統合失調症の症状が現れて突然叫びだした姉。姉を「問題ない」と医療から遠ざけ南京錠をかけて家に閉じ込めた、医師で研究者の両親。そして変わってしまった姉を心配し、両親の対応に疑問を感じながらもどうすることもできずにいた弟。 20年にわたって自身の家族にカメラを向け続けた弟・藤野知明監督によるドキュメンタリー映画『どうすればよかったか?』は、公開と同時に大きな反響を呼び、異例の大ヒットを記録した。 本書では、映画に入れることを断念したショッキングな家族の事実をはじめ、家族と過ごした時間の中で味わった悲しみ、怒り、混乱、葛藤、喜び、希望など、映像では伝えきれなかった様々な思いを監督自身の率直な言葉で明かしている。 息を呑むような衝撃とともに突き付けられるのは、「家族とは?」「人生とは?」、そして「どうすればよかったか?」という答えのない問い――。 ままならない思いを抱えながら、それでも誰かと生きようとする、すべての人に捧げるノンフィクション。
-

集中講義!日本の現代思想 ポストモダンと「その後」を問いなおす
¥1,980
版元:NHK出版 著:仲正昌樹 B6判並製 320ページ 2025年12月刊 いま、「思想」は日本を分析しうるか? 丸山眞男や吉本隆明など戦後思想との比較を踏まえ、浅田彰や中沢新一らの言説からポストモダン思想の功罪を論じたロングセラーが、約20年の時を経てアップデート! 80年代に流行した「現代思想」は海外思想をいかに咀嚼して成り立ち、若者を魅了しながら広がり、やがて終焉へ向かったのか。その後、ゼロ年代以降の「哲学・思想」ブームによって、多くの「スター」が輩出されても、彼らを軸にした思想の流れが生まれてこないのはなぜなのか──? ますます個人主義化する世界で、社会を分析する道具としての「思想」の可能性をいま改めて問う。2万超の新章「二一世紀に”日本の現代思想”は存在するか」を加えた決定版。
-

不安の時代 スマホ・SNSが子どもと若者の心を蝕む理由
¥3,080
版元:草思社 著:ジョナサン・ハイト 訳:西川由紀子 四六判上製 480ページ 2026/01刊 2010年代初頭、最初のZ世代が10代になった直後、世界中で10代の不安・うつ・自傷・自殺が急上昇し始めました。それは、スマートフォンが急速に普及した時期でもあります。因果関係はあるのでしょうか? 実際、スマホの登場で「子ども時代」のあり方は決定的に変わりました。 スマホが気になって、一緒にいるクラスメイトと会話が起こらない。注意力も散漫に。また、ネットいじめが横行するように。 女子は、SNSで「イケてる」女の子の写真やショート動画を見ることを、やめられなくなりました。それらと自分を比べて自己評価が低下、不安で憂鬱に。女子のほうが、自傷・自殺の上昇率が大きくなっています。 男子は、オンラインゲームとネットポルノに夢中になり、現実世界での経験が減少。現実での挑戦や冒険の機会が失われ、その結果いつまでも自信が持てず、無力感に苦しむようになっています。 親たちは、つねに子どもの位置情報をスマホで確認しないと心配だと感じるようになりました。 本書は、このような「スマートフォン中心の子ども時代」を経験した子ども・若者の心の健康の悪化とその原因をデータで提示、さらに具体的解決策まで示した世界的ベストセラーです。すべての親と教育者、子ども・若者にかかわる人たち必読の書と言えるでしょう。
-

なぜ「地方女子」は呪縛になるのか
¥1,045
SOLD OUT
版元:集英社 著:寺町 晋哉 新書判 206ページ 2026年1月刊 大学進学において、生まれ育った地域、性別、通っている高校、保護者の学歴など、特に多くの壁=社会的諸条件を乗り越えなければならないのが「地方女子」。 個人の努力や意志の問題に矮小化すると、「壁を乗り越えられないのは自己責任」という重荷を子どもたちに背負わせかねず、「地方女子」を呪縛にしてしまう。 選択の背景にある「当たり前」はどのようにつくられているのか──。 本書では「地方女子」の置かれた現状を教育、制度、経済、社会意識、ジェンダーなど多角的な視点から分析し問う。
-

自己決定の落とし穴
¥990
版元:筑摩書房 著:石田光規 新書判 208ページ 2025年8月刊 自分で決めたはずなのに息が詰まるのはなぜ? 自分のことは自分で決める。ひとりを尊重する――善いことのはずなのにどこか息苦しいのはなぜ? 「自己決定」をめぐるこの社会の自縄自縛をときほぐす。
-

問いつめられたおじさんの答え
¥2,420
版元:石原書房 著:いがらしみきお 四六判 並製 144ページ 2026年1月刊 耳の聞こえないひとは、どうやって聞くの? どうしてみんな、携帯ばっかり見てるの? 家族って、なんですか? どうして嘘をついちゃいけないの? どうしてこんなに暑いの? 友だちって、必要? 勉強って、役に立つの? 人はどうして死んじゃうの? ――子供に訊かれたら困るその質問、おじさん=いがらしみきおが答えます。「webちくま」(筑摩書房)の人気エッセイ連載、待望の書籍化! 『ぼのぼの』『I【アイ】』の漫画家・いがらしみきおがまっすぐ、そしてユーモラスに綴る、素朴な疑問への答え。 東日本大震災とコロナ禍を経て、いがらしさんの世界との向き合い方がやさしく灯る、子どもにも大人にも面白い「人生の最初の問い」に寄り添う一冊。 各界の大人たちからの書き下ろし質問への回答を併録。
-

言霊の舟 白川静・石牟礼道子 往復書簡
¥2,860
版元:藤原書店 著:白川静・石牟礼道子 編:笠井賢一 四六判並製 272頁 2025年11月刊 現代の失楽園の作者――白川静 現代の知をよみがえらす学祖――石牟礼道子 白川静(1910-2006)の文字学に大きな衝撃を受け、師と仰いだ石牟礼道子(1927-2018)。文字以前の原初的意識への憧憬を抱き続けた石牟礼に、白川の学問と思想は何を刻みつけたのか。1993年の初邂逅から白川が没する2006年までの60通の未公開書簡と、生涯に2回だけ実現した対談を収録し、言葉と芸能、そして魂をめぐる二人の交流の深層を明かす。
-

住む権利とマイノリティ 住まいの不平等を考える
¥3,080
版元:青弓社 編:青弓社編集部 四六判並製 228ページ 2025年12月刊 執筆者:金井 聡/杉野衣代/大澤優真/志村敬親/岡部 茜/植野ルナ/永井悠大/龔軼群 DV被害者や外国籍者、中・高年単身女性ほかマイノリティに焦点を当て、住まいをめぐる現況と課題を詳述する。さらに、支援に取り組むNPOと企業が改善策を提示する。住まいの問題を多角的に捉え、住まいの権利をマイノリティの視点から照射する。 都市部でのマンション価格や家賃の高騰が報じられる一方、部屋を借りることが難しい人たちの存在が可視化され、住まいをめぐる格差の問題は近年ますます注目を集めている。2020年に新型コロナウイルス感染症が感染拡大した際には、ホームレスやネットカフェ難民の問題など、住まいの格差が顕在化した。 現在の日本では、住む権利/住まいの権利が全員に保障されているとはいいがたい。入居を断られる、シェルターに入れない、入ったとしても環境が悪く落ち着いて暮らせない。「住宅弱者」「住宅確保要配慮者」などの言葉が広まり、住宅を確保するための法整備が進んできているが、安定した住まいから排除され不安定な生活を余儀なくされる人たちも存在している。 本書は、DV被害者や外国籍者ほかマイノリティに焦点を当て、住まいをめぐる現況と課題を詳述する。さらに、ホームレス支援に取り組むNPOと、住まい探しの状況改善に取り組む企業が、それぞれの視点から改善策を提示する。最も身近な「住まい」の問題を多角的に捉え、住まいの権利をマイノリティの視点から照射する。
-

無敵化する若者たち
¥1,760
版元:東洋経済新報社 著:金間大介 四六判並製 302ページ 2026年1月刊 ■■■『先生、どうか皆の前でほめないで下さい』待望の続編!■■■ あなたの部下やお子さん、こんな感じじゃないですか? 仕事にも出世にも興味がない 締切が来ても残業しない 権利主張が強い 自己評価が高い アウトじゃないけど微妙に失礼 安定志向が強い いつでも親が味方 先輩世代から大切にされる 無菌化された労働環境 飲み会でも守られる 自分がよければそれでいい 日本の衰退を気にしない 将来展望がない日本でも十分幸せ…… 前著で若者たちの「いい子症候群」をリアルに描き話題となった著者が、最新の知見とデータをもとに、再び若者心理の謎に迫ります!
-

「ソロ」という選択 自分だけの特別な人生を築く
¥3,080
版元:青土社 著:ピーター・マグロウ 四六判並製 320P 2025年11月刊 ひとりがダメだなんて誰が決めた! 社会は結婚を前提にできていて、独身者向けの本はいいパートナーを見つける方法ばかり……でも、それって本当に自分にとって必要なことなの? ソロ・プロジェクトを唱導する著者が、ひとりでいることの喜び、社会性、充実感、そして規則にしばられない最高に幸せな人生の送りかたを教えてくれる。そうだ、自分は自分のままでいいんだと勇気づけられる。ひとりの人も、パートナーがいる人も、ここから「ソロ」をはじめよう
-

組織をよむ。研究会
¥1,500
SOLD OUT
企画・編集:合同会社Kokkara エキスパート:佐宗邦威・松村圭一郎・上平崇仁・樋口あゆみ・吉田満梨 A5判並製 2025年10月刊 「組織をよむ。」研究会は、豊かな組織の見立て方(=よみ方)を養う研究会です。組織のよみ方を「周辺の視点」から語ることのできるエキスパート(戦略デザイナー、文化人類学者、社会学者、デザイン研究家、経営学者)と約20名の研究員が共に、組織の豊かな見立て方や理解の方法を探求します。 ビジネスセオリーに則った内容ではないため、「明日の組織」には役立ちにくいかもしれませんが、「明後日の組織」を考えるには持ってこいのネタがまとまっています。
-

脱走論 うつの時代の新しい倫理
¥3,300
版元:青土社 著:フランコ・ベラルディ 訳:杉村昌昭 四六判並製 248P 2025年12月刊 脱走こそ、唯一可能な倫理的選択にして合理的戦略である 経済成長の神話を支え暴力を生み出しつづける、あらゆる行為を放棄すること。ここにこそ荒廃する時代を生き延びる唯一の道がある。世界を覆う「うつ状態」を資本主義社会に対する抵抗として積極的に捉え返した、退行の時代のための新たなマニフェスト。
-

平和と愚かさ
¥3,300
版元:ゲンロン 著:東浩紀 四六判並製 500頁 2025年12月15日発行 ぼくたちは政治について語りすぎている。そのせいで平和から遠ざかっている。 ウクライナ、中国、ユーゴスラヴィア、ベトナム、そしてアメリカ……。戦争の記憶をめぐり、平和について考えた哲学紀行文集。ひとは政治の時代をいかに抜け出せるか。『動物化するポストモダン』の著者による、「考えないこと」からの平和論。
-

ちゃぶ台 14 特集:お金、闇夜で元気にまわる
¥1,980
版元・編集:ミシマ社 四六判変形 158 ページ 2025年12月16日刊 日経株価が最高値になっても、物価高・米不足は起き、暮らしの経済は疲弊―― 生活者が生き生きする、別の「お金のまわり方」が、「闇夜」=ちいさな経済圏に広がっているのでは これを探るため、創刊10周年を迎えた今号はW特集を掲げます! 特集① お金、闇夜で元気にまわる ・書店と出版社が組み、限界を超えたイベント 「ちゃぶ台フェスティバル@ウィー東城店」徹底レポート! 目撃者・松村圭一郎(論考)「なんのための『経済』なのか?」 主催者・佐藤友則(インタビュー)「経営の発想の転換で本屋さんをくすぐっていく」 ・湯澤規子(随筆)「テーマの火は闇夜に灯る」 ・高橋久美子(エッセイ)「土の近くでまわる、お金のはなし」 ・土井善晴(随筆)「料理とお金」 ・平川克美(論考)「隠居ジジイの家計簿」 特集② 十年後の移住のすすめ ・本誌創刊号「移住のすすめ」を読み、本当に周防大島に移住した若者が寄稿 垂井綾乃「周防大島に吹く風に身を任せていたら」 ・移住先輩世代が周防大島の「今」を証言 内田健太郎(エッセイ)「鯖とヘソ娘」 中村明珍(コメント)「十年後の移住のすすめ」 ●巻頭漫画:益田ミリ「今日の人生 出張版」
-

沖縄社会論 周縁と暴力
¥2,970
版元:筑摩書房 著:上越正行 解説:石岡丈昇・上原健太郎・上間陽子・岸政彦 四六判上製 464頁 2025年12月刊 暴走族のパシリにはじまり、沖縄で調査を続けた伝説のフィールドワーカーによる遺稿集。パシリ論、沖縄社会論、暴力論の各部に解説を付す。 暴走族のパシリにはじまり、沖縄で調査を続けた。 『ヤンキーと地元』を書いた伝説のフィールドワーカーによる遺稿集。 2024年12月9日に急逝した、社会学者・打越正行さんの遺稿集を一周忌に合わせて刊行。 『ヤンキーと地元』(2019年3月刊、2024年11月ちくま文庫化)で打越さんは、沖縄の暴走族の「しーじゃ・うっとう(先輩・後輩)」関係などをもとに、建設業で生きるリスク層の生活を描かれました。地元の人間でも調査できない領域にパシリとして入っていった著者の本は、ナイチャーの書いたものとして驚きをもって迎えられ、第六回沖縄書店大賞沖縄部門大賞を受賞するなど高い評価を得ました。 本書は打越さんの遺した、パシリ論、沖縄社会論、暴力論の3部からなり、石岡丈昇、上原健太郎、上間陽子、岸政彦各氏の解説を付す。
-

「恥」に操られる私たち 他者をおとしめて搾取する現代社会
¥3,080
版元:白揚社 著:キャシー・オニール 訳:西田美緒子 四六判並製 320ページ 2025年12月刊 私たちはなぜ恥ずかしい思いに悩まされるのか? そしてなぜ「恥ずかしい」人や行為を非難してしまうのか? 体型や容姿に対する侮辱、生活保護に対するバッシング、キャンセルカルチャーなど、個人に対する非難や攻撃はどんどん過激化している。この現象の裏には、「恥ずかしい」と悩む私たちの気持ちにつけこみ、利益を得ようとする企業や社会システムが潜んでいるのだ。 どうすれば「恥」に苦しめられる現状を打破できるのか? 貧困や依存症の問題、SNSでの攻撃や暴言、コロナ禍での対立などさまざまな事例を挙げながら、「恥」がどのように生み出されて利用されているかを暴き出す異色の社会論。
-

ペンと剣 増補新版
¥2,530
版元:里山社 著:エドワード・W・サイード 聞き手:デーヴィッド・バーサミアン 訳:中野真紀子 四六判変形並製 320ページ 2025年12月10日刊 パレスチナの闘う知識人・サイードの入門書を復刊。和解と共生をあきらめない思想をわかりやすい言葉で伝える名インタビュー集。 分断が進む世界への絶望に抗うために 広い視野で希望を見出すサイードの思想 西洋中心の価値観に異議を唱え、アカデミズムの枠を越えて政治に声を上げた人物像を浮かび上がらせる、サイードをこれから読む人にも最適な一冊。西洋の視点を通して表象されたアラブ・イスラム世界のステレオタイプを、西洋が支配に利用してきたことを論じ、権力と知識の関係を問い直す古典的名著『オリエンタリズム』。西洋の文化や文学が植民地支配や帝国主義と深く結びつき、権力構造に奉仕してきたことを分析する『文化と帝国主義』。自著をわかりやすい言葉で語り、パレスチナ問題に通ずる世界の構造を広い視野で捉え「和解と共生」への道を示すインタヴュー集。 「パレスチナという理念は、他者との共生、他者の尊重、パレスチナ人とイスラエル人とが互いに相手を認めるという理念である」
-

帰りに牛乳買ってきて 女ふたり暮らし、ただいま20年目。
¥1,540
版元:柏書房 著:はらだ有彩 A5判並製 208ページ 2025年11月刊 《ふたりで楽しく暮らすことにしました、それも一生》。20年にわたる著者とルームメイトとの共同生活を描くコミックエッセイ。
-

ル・ボン 群集心理 「みんな」には騙されない
¥1,210
版元:NHK出版 著:武田砂鉄 四六判並製 144ページ 2025年11月刊 世の中の空気に抗い、「自分」で考え抜くために。 近代社会と人間の心理に独自の視点で鋭く斬り込んだ『群衆心理』。良識ある個人はなぜ、いかにして暴徒と化すのか。人々の思考を麻痺させ自立性を削り取るために指導者はいかなる手段を用いるのか。SNSが発達し群衆心理の感染力が一層強まるなか、その暴走を止めるためにこれから何ができるのか。 政治をめぐる対立からネット炎上まで、「大きな主語」に覆われた現代日本の抱える問題に引き寄せながらル・ボンの議論を読み解く。Eテレ「100分de名著」テキストに書き下ろしの特別章・ブックガイドなど大幅加筆をして書籍化。
-

苦痛の心理学 なぜ人は自ら苦しみを求めるのか
¥3,300
版元:草思社 著:ポール・ブルーム 訳:夏目大 四六判並製 392頁 2025年11月刊 人はなぜ倒錯的な痛みを求めるのか。その理由を心理学、脳科学などの視点から科学的に説き明かす。『反共感論』の著者による、苦痛からみる「逆説的幸福論」。
-

エトセトラ VOL.14 特集 SRHR 福田和子・高井ゆと里 特集編集
¥1,650
版元:etc.books 特集編集:福田和子・高井ゆと里 A5判並製 132ページ 2025年11月刊 「わたしたち」の場づくり、コミュニティ、言葉をアーカイヴする。 ウーマンリブから生まれたレズビアン・コミュニティ、伝説のレズビアン&バイセクシュアル雑誌、そして、Xジェンダーの語りや、様々なセクシュアルマイノリティの集まれる場所……。 フェミマガジン13号目は、「LGBTQ」から消されてしまいがちな女性やノンバイナリー/Xジェンダーの人々による、場所づくりや運動を記録する特集号。多数のインタビュー、寄稿、読者投稿「自分の存在を消されたと感じたことはありますか?」など。
-

他人がこわい あがり症・内気・社交恐怖の心理学
¥2,640
版元:紀伊國屋書店 著:アンドレ・クリストフ レジュロン・パトリック ペリッソロ・アントワーヌ 監訳:高野優 訳:田中裕子 野田嘉秀 四六判並製 376ページ 2025年11月刊 治療の目標は、「人前で顔が赤くならない」ことではない。 「人前で顔が赤くなるのを受け入れる」ことだ。 そして、それを他人に気軽に話せるようになることである―― ●ドキドキして会議で発言できない ●初対面の人と話ができない ●人から見られていると字が書けない ●人前で赤面するのが怖い…… 対人関係において、不安や恐怖(社交不安)を感じる人は多い。どのような形で現れるかは人それぞれだが、放っておくと仕事や日常生活に影響が及びかねない。 人とのかかわりに強い不安や恐怖を感じ、日常生活に支障をきたす〈社交不安症〉は、全国で約200万人の患者がいるとされ、日本ではうつ病の次に多い精神疾患だが、治療法や予防法があることが一般に知られていない。 フランスの人気精神科医が、豊富な実例や図表、コラムを交えながら、〈社交不安〉に悩む人の心のメカニズムから克服法までをやさしく解説した「読む心理療法」。 フランスで30年間売れているロングセラーに、新しい知見や治療法、SNSの普及やコロナ禍がもたらした影響などを追加した改訂版!