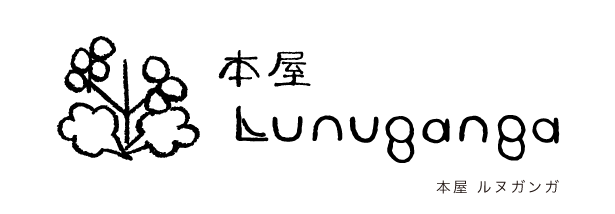-

現代の道具のブツリ
¥2,640
SOLD OUT
版元:雷鳥社 文:田中幸・結城千代子 絵:大塚文香 A5判変形(200×100)コデックス装 292ページ 2026年1月刊 私たちの生活をとりまく便利な道具と目に見えない力。 そこには光、音、熱、波、粒の世界がある。 知れば知るほど暮らしがもっと「愉快」になる! 型破りで、親しみやすい、物理学の副読本。 待望の『道具のブツリ』第2弾! テーマは、現代の暮らしを支える道具たち。 冷蔵庫、スマホ、時計、日傘、体温計、電子レンジ……。 本書では、電磁波から放射線、原子や電子の世界まで、 「目に見えない力」をあつかう25個の道具のブツリを紹介します。 見えない体の中を覗くX線、水分子を揺らして温める電子レンジ、 気化熱で冷やし続ける冷蔵庫、300億年に1秒しか狂わない時計……etc. 見たいものを見たい、より美味しく食べたい、外部の脅威から身を守りたい――。 そうした人間の欲望から生まれた生活道具を、 「みる」「つたえる」「たべる」「ふせぐ」「はかる」の5つの章に分け、 物理を専門とする教師ふたりが、道具とブツリの面白い関係について語ります。 難しい公式や計算はいっさい出てきません。 一見すると「複雑でしょ」と思われがちな道具も、 そのしくみを解きほぐせば、素朴な「物のことわり(自然法則)」が潜んでいるものです。 前作『道具のブツリ』の仕様はそのまま! パタンと勢いよく開くコデックス装、開くと正方形になる縦長の判型、 色やテクスチャを版画のように重ねた大塚文香さんの挿絵も、 ページ数増量でお愉しみいただけます。
-

道具のブツリ
¥2,420
SOLD OUT
版元:雷鳥社 文:田中幸・結城千代子 絵:大塚文香 A5判変形(200×100)コデックス装 272ページ 2023年8月刊 理にかなったものは美しい 25個の生活道具とそこに隠されたブツリをひも解く、 風変わりで、やさしい、物理学の入門書。 身の回りのものはすべて自然の原理や法則のもと成り立っています。 役に立たないと思われがちな中学・高校で習うブツリが、 実はさまざまな道具がもつ「用の美」の基礎になっているのです。 本書は、誰もが一度は使ったことのある生活道具を 「ながす道具」「さす道具」「きる道具」「たもつ道具」「はこぶ道具」の5つの章に分け、 物理を専門とする教師ふたりが、ああでもない、こうでもないと呟きながら、 道具とブツリの面白い関係について語ります。難しい公式や計算はいっさい出てきません。 点で突き刺すフォーク、慣性の法則で水を切るざる、 無限の刃渡りをもつピザカッター、空中の支点でてこを動かすハサミ…etc. 紀元前に生まれたスプーンや車輪など、 今なお変わらない道具の形やしくみにもう一度目を向けることで、 長い年月を経ても廃れない道具のデザインや機能が見えてくることでしょう。 開くと正方形になる縦長の判型、開きのよいコデックス装。 そして色やテクスチャを版画のように重ねた、 独特な風合いのある大塚文香さんの挿絵にもご注目!
-

体育会系 日本のスポーツ教育が創った特異な世界
¥1,056
版元:中央公論社 著:小野雄大 新書判 240ページ 2026/1/22刊 大学をはじめ学校の運動部出身で特有の価値観・行動様式を持つ体育会系。厳格な上下関係、集団規律・根性重視などを特徴とし、爽やか、暴力的、勉学が苦手、就活に有利など様々に語られてきた。本書はその起源から、先輩・後輩関係の調査、スポーツ推薦入試の軌跡と現状、就職後のキャリア形成の困難などを多角的に描く。近年、深刻化する不祥事の歴史も追い、数百万人規模とも思われる日本独自の体育会系の実態を描く。
-

スペクテイター 55 にっぽんの漂泊民
¥1,320
版元:エディトリアル・デパートメント B5変型 160頁 2026年1月刊 かつてこの国には、社会の枠の外側でひっそりと、しかし確かな意志をもって自由に生きた「漂泊民」と呼ばれる人々がいた。 彼らはいつ、どこから現れ、どのような道を歩んだのか。 個人の行動が可視化され、管理が加速する現代において、定住を拒む「漂泊」という生き方は、いかなる意味を放つのか。 日本の歴史と民俗を辿り、現代人が失った精神の根源を掘り下げる、あらたな旅への案内。 *導入まんが「漂泊民って、なんだろう?」アシタモ *図解「絵でみる漂泊民」河井克夫 *インタビュー ・「サンカの民ってなんだろう?」磯川全次(在野史家) ・「人はなぜ、サンカに自由を見るのか?」今井照容(もとサンカ研究会) ・「サンカたちとの短かい交流」清水おさむ(劇画家) ・「21世紀 民俗巷談」堤邦彦(国文学者) *まんが「木霊」勝又進 *まんが「丘の向こう」まどのかずや *論考「未来はノマド? 移動する人々の過去・現在・未来」長沼行太郎 *寄稿「サンカサークルを こうして立ち上げた」アラカワ(サークル代表) *講座「民俗学のABC」ノンバズル企画
-

遥かな都
¥3,300
SOLD OUT
版元:作品社 著:池澤夏樹 四六判上製 304P 2026年1月刊 書物の中と博物館の遺物の間にしかない幻影の都市、アレクサンドリア。 その蜃気楼のような姿を追って遊歩する歴史紀行。 池澤訳、E・M・フォースター『ファロスとファリロン』を併録 《アレクサンドリア。紀元前三世紀にアフリカの地中海岸に造営されたこの都は二千数百年に亘って次々に支配する民族を替えながら繁栄し、一九五二年に至って本来の主人であるべきエジプト人の手に渡った。/それまでの間、文化的なものはすべて地中海の北岸からあるいは東のアラビア半島からやってきて、エジプト人はただ住民に穀物を供することだけを求められた。/だから、エジプト革命で都市の相貌はすっかり変わり、それ以前の姿は文学の中にしか残らなかった。華麗で壮大な、言葉だけで築かれた大厦高楼の集合。古代の詩人や思想家に始まって近代ギリシャ語の詩人K・P・カヴァフィス、イギリス人であるE・M・フォースターとロレンス・ダレルの作品群。/ぼくは若い時にこの文学の都市に出会って夢中になり、いくつかの文章を書き、翻訳もした。気がつけばこれが相当な量になる。そこでこれを一巻に纏めようと思い立った。》││本書「はじめに」より
-

平和と愚かさ
¥3,300
版元:ゲンロン 著:東浩紀 四六判並製 500頁 2025年12月15日発行 ぼくたちは政治について語りすぎている。そのせいで平和から遠ざかっている。 ウクライナ、中国、ユーゴスラヴィア、ベトナム、そしてアメリカ……。戦争の記憶をめぐり、平和について考えた哲学紀行文集。ひとは政治の時代をいかに抜け出せるか。『動物化するポストモダン』の著者による、「考えないこと」からの平和論。
-

「酔っぱらい」たちの日本近代 酒とアルコールの社会史
¥1,034
版元:KADOKAWA 著:右田裕規 新書判 216ページ 2025年12月10日刊 「絶対に終電で帰る」の起源とは? 「飲酒」と「労働」の20世紀史に迫る 「今日は花金」「一杯くらい飲めないと」「絶対に終電で帰る」 「泥酔しても8時出社」 ―― 【デキる奴ほど酒を飲む】はいつ生まれ、なぜ消えゆくのか? 近世まで、飲酒は非日常を体感する儀礼的な営みであり、祝宴では酔いつぶれることこそが「マナー」だった。工業化の過程で、都市に集まった人びとは翌日の労働のために飲酒を規制しはじめる。好んで夜の街に繰り出しながら、酔いを隠し、記憶喪失を恐れ、「ワリカン」でしめやかに終わる。こうした一見矛盾する飲み方は、どのような過程で都市民たちに内面化されていったのか。近代化の隙間で労働の日々を生きた日本人の秘史を、気鋭の社会学者が炙り出す。
-

昭和界隈 写真でタイムトラベル
¥2,200
版元:朝日新聞出版 協力:朝日新聞フォトアーカイブ B5判並製 224ページ 2025年11月20日刊 「昭和100年」に写真で振り返る 人々の暮らしと時代の熱気。 人間くささ、暮らしのあたたかさが匂ってくる。 (映画監督 山田洋次) 朝日新聞の人気連載「朝日新聞写真館」をもとに再構成。 朝日新聞や「週刊朝日」「アサヒグラフ」などの雑誌に掲載された 報道写真のアーカイブより、昭和の人々の暮らしや社会風俗、 時代の熱量に満ちた写真を選りすぐり、ご紹介します。
-

ノスタルジアは世界を滅ぼすのか ある危険な感情の歴史
¥2,420
SOLD OUT
版元:東洋経済新報社 著:アグネス・アーノルド=フォースター 訳:月谷真紀 四六判並製 386ページ 2025年8月刊 あなたの「懐かしい」は誰かの「武器」になる。 人類史上、最も危険で、最も癒され、最も儲かる「エモい」感情の正体。 政治やビジネスを動かし、消費を煽る、知られざる力とは。 本当に「昔は良かった」のか。 「希望は過去にしかない」のか。 時代を超えて誰もが持つ複雑かつ普遍的な感情の魅惑的な歴史とは。 過去5世紀にわたる影響力と、その両義性の謎を明らかにする。 「あの頃は良かった」という、甘くも切ない感情「ノスタルジア」。 その根源は17世紀スイスの「望郷病」にあり、兵士や奴隷の死因となる病とされた。 しかし時代とともにその姿を変え、20世紀以降は消費者の購買意欲を刺激する「ノスタルジア産業」へと変貌。 さらに現代では、トランプ大統領のスローガン「Make America Great Again(アメリカを再び偉大な国に)」に象徴されるように、政治家が有権者の心を掴むための戦略としても利用されている。 本書は、世の中を動かす「危険な感情」としてのノスタルジアの変遷を読み解き、その知られざる力と巧妙なメカニズムを解き明かす。 トランプが2016年に続き再び「アメリカを再び偉大な国に」というノスタルジックなスローガンを掲げて大統領選に勝利してしまったことなどから、ノスタルジアは保守的で後ろ向きな感情だと悪いイメージを持っている人のほうが多いのかもしれない。 だが、ノスタルジアは必ずしも有害な感情ではない。 17世紀では「死に至る病」とも考えられていたノスタルジア。しかし、脳科学が発達した現代では「古き良き時代」を思い出すときに抱く懐かしい気持ちにセラピー効果があることもわかってきた。過去のシンプルな日々への憧れとして、商品や「ミニマリズム」のようなコンセプト、さらには政策を売り込むために広告代理店や政治家がノスタルジアを利用することまで行われている。ノスタルジアは良くも悪くも社会的、政治的感情であり、社会的に有効に利用される反面、悪用されやすくもあり、時代の不安を反映するものであり続けている。本書では、ノスタルジアの複雑な感情の魅惑的な歴史が、過去5世紀にわたってどのように発展してきたかを鮮やかに探る。
-

日本遠国紀行 消えゆくものを探す旅
¥3,300
版元:笠間書院 著:道民の人 A5判並製 384頁 2025年10月刊 日本各地を旅し、美しい写真や親しみやすいレポートを通じてSNSで人気を集めている「道民の人」の集大成といえる紀行文 故郷・北海道の廃墟で産業と都市の盛衰に思いを馳せ、秋田で村を守る奇怪な神・人形道祖神を巡って地元の人による「衣替え」を手伝い、青森では現役のイタコに亡き祖父の霊を降ろしてもらい、長崎では隠れキリシタンの子孫からその独特の正月飾りの作り方を習う……。 日本各地を旅し、美しい写真や親しみやすいレポートを通じてSNSで人気を集めている「道民の人」による、これまでの集大成といえる紀行文。 「忘れられがちな地方の風習や暮らしぶりを伝えたい、失われつつあるものを記録として残したい」という信念のもと、実際に現地を訪れて地元の人々と交流し、風習の背景にある歴史まで幅広く研究してきた長年の成果を、多数のカラー写真とともにまとめました。 過疎化や都市部への人口集中が進み、自然災害の際に「そんな不便な場所に住まなければいいのに」などと言われることもある地方にも、そこでしか成り立たない独自の歴史と文化があること。 日本のなかにあって「遠国=遠い場所」のようになってしまった地方の豊かさに、改めて気付かせてくれる1冊です。
-

オーラル・ヒストリー入門
¥1,078
SOLD OUT
版元:筑摩書房 編:佐藤信 新書判 288ページ 2025年10月 「歴史を聞いて、残す。」大学から公民館まで、政治学や社会学におけるインタビューの実践例を通して、そのノウハウを学べる一冊。
-

食権力の現代史 ナチス「飢餓計画」とその水脈
¥2,970
版元:人文書院 著:藤原辰史 四六判並製 324ページ 2025年9月刊 なぜ、権力は飢えさせるのか? 飢餓という暴力の歴史をたどる -----史上最大の殺人計画「飢餓計画フンガープラン」。ソ連の住民3000万人の餓死を目標としたこのナチスの計画は、どこから来てどこへ向かったのか。その世界史的探究の果てに、著者は、「飢餓計画」と現代世界の飢餓を結ぶ重要人物を探り当てる。飢餓を終えられない現代社会の根源を探る画期的歴史論考。 飢餓は発見後に実在化したのではない。飢餓それ自体が、依然として、問題化と非問題化のあらそいの場なのだ。ナチスの飢餓もイスラエルの飢餓もソ連の飢餓もそれは変わらない。では、この飢餓を再び自然化する力の源とはなにか─ 本書は、このような問いから始まる。(…)飢餓は人を平等に殺さない。ここに介入するのは自然というよりは、社会であり制度であり政治である。「序章」より 第一次大戦から第二次大戦を経て、イスラエルのガザの虐殺までの現代史を、食を通じた権力の歴史、そして「施設化」した飢餓の歴史として描く!
-

よみがえる美しい島 産廃不法投棄とたたかった豊島の五〇年
¥2,860
SOLD OUT
版元:日本評論社 著:大川真郎 四六判上製 352ページ 2025年5月刊 わが国最大の産廃不法投棄に見舞われた瀬戸内海の豊島。自然豊かなふるさとを取り戻すために立ち上がった住民たちの勇姿を描く。
-

SPECTATOR 54 パンクの正体
¥1,320
版元:エディトリアル・デパートメント B5変型 160頁 2025年8月刊 1970年代中頃にパンク・ロックが大流行した当時のイギリスの社会状況は、現在の日本とよく似ている。 原油価格の高騰、極端なインフレ、上昇する失業率、上流階級への不満——そうした社会に対する鬱憤が爆発し、若者による文化革命が起こった。 パンクとは何か? どのようにして生まれ、社会をどう変えていったのか? 関係者への取材と文献調査を通じて、その正体を明らかにする。
-

男が「よよよよよよ」と泣いていた 日本語は感情オノマトペが面白い
¥1,254
SOLD OUT
版元:光文社 著:山口仲美 新書判 416ページ 2025/08刊 「ワンワン」など動物の声や「ドッカーン」などの物音、「ひらひら」など物事の状態や様子を写す言葉「オノマトペ」を日本人はこよなく愛してきた。本書では日本人の泣く声や様子、笑う声や笑う様を表わすオノマトペに焦点を絞り歴史の糸を手繰り寄せる。「ウェラウェラ」「ツブツブ」「ホヤホヤ」など予想外のオノマトペが続出、そこに潜む日本人の認識の仕方や時代性も追究。オノマトペ研究の第一人者による斬新な日本語の歴史。
-

Tシャツの日本史
¥2,200
版元:中央公論新社 著:高畑鍬名 四六判並製 256ページ 2025/8/21刊 夏目漱石の「赤シャツ」、石原裕次郎と太陽族、そして菅田将暉が変えた運命――ファッション史の壮大な死角であるTシャツには、日本の同調圧力と美の仕組みが隠されていた。〈裾〉をインするかアウトするか? 激動の150年を記録した前代未聞のTシャツ史。
-

世界猟奇殺人者事典
¥2,970
版元:玄光社 著:朝里樹 A5判並製 288ページ 2025/07/23刊 人はなぜ、人を殺すのか――。 快楽、金銭、嫉妬、信仰、あるいは理解不能な衝動。古今東西で実際に発生した猟奇殺人事件の中から、特に異様なものを厳選し、連続殺人犯やシリアルキラーを中心に、500件の事例をまとめました。著者は『日本現代怪異事典』などで知られる怪奇コレクター・朝里樹。実話を扱う本書ではあくまで資料性を重視し、事件の動機や背景、残忍な手口の詳細を記録しています。ホラーやミステリーの創作ネタ帳としても活用できる一冊です。
-

記憶の旗を立てる 8月15日の日記集
¥1,980
SOLD OUT
発行所:いい風 作:椋本湧也 装丁:古本実加 装画:三瓶玲奈 W120×H210×D18mm/並製 428ページ 2025年8月刊 他者の体験の記憶を、いかに受け継ぐことができるだろうか—。94歳の祖母に戦時体験をインタビューし、その録音音声を聞いた71名の読み手が綴る「8月15日」の日記集。 「あんたたちにはわからんよ。体験してないんだから。それでもね、あんたたちがどう受けとめて、戦争しないように持っていくか。もうそれしかないよ」 (祖母へのインタビューより) 体験のない私たちは「軽い」。けれども軽いからこそできることがまたあるはずで、その方法を自分たちの手ごたえを通して試し・確かめていくこと。「わかりえない」ことを受けとめた上で、いくつもの「今」から何度でも思い出し、重ね描きつづけていくこと。それがこの本の主題です。 祖母へのインタビューを冒頭13ページにわたって掲載。また1945年の8月15日に書かれた日記を蒐集し、25名分の引用を織り込みました。 この本に書かれたいくつもの個人的な体験の記憶が、読み手の記憶と結びつき、それぞれの生活の中で新たな意味を帯びることを願っています。 戦後80年の今年、ぜひ手に取っていただけたら幸いです。
-

戦前 エキセントリックウーマン列伝
¥2,420
SOLD OUT
版元:左右社 著:平山亜佐子 四六判並製 314ページ 2025年07月刊 〈偉業〉と〈異業〉を成し遂げた、戦前の女20人 「エキセントリック」=風変り、常識外れ、奇抜、突飛の意味。 明治、大正、昭和初期。女性にとって今よりもはるかに抑圧の多かった時代にも、自分の心の声に従って生きたエキセントリックな女たちがいた! 「個性的」という言葉すら生ぬるい女たちの生き様を、愛を込めて描く傑作ノンフィクション。
-

生命と時間のあいだ
¥1,815
版元:新潮社 著:福岡伸一 四六判並製 224ページ 2025年7月刊 ダ・ヴィンチ、ダーウィン、ガリレオ・ガリレイ、フェルメール、坂本龍一、手塚治虫、村上春樹、安部公房、丸谷才一……彼らの作品に立ち上がる時間の流れを捉え、世界と生命の解像度を一新する。近代科学で見えなくなった時間のパラドクスを解き明かす、著者真骨頂の新たな時間論。
-

空海
¥4,950
版元:講談社 著:安藤礼二 A5判上製 560ページ 2025年05月29日 人間中心主義でやってきた世界は繁栄のなかに滅びが見え始めている。人間中心的な世界認識を改めなけれならない。いまあらためて空海を読み直さなければならないのである。 空海は二つの「頌」を残した。『声字実相義』と『即身成仏義』の核心をただそれだけで語りきってしまった「頌」(「詩」)である。空海の「詩」は、膨大な仏典を読み解いた上で可能になったものだ。『大日経』と『金剛頂経』 の交点、 胎蔵界曼荼羅と金剛界曼荼羅の交点に、空海は自身の信仰の体系にして思想の体系を築いたのだ。胎蔵界曼荼羅と金剛界曼荼羅を見れば『大日経』と『金剛頂経』の異なることは明らかである。空海は異なる経典を統合してみせる。生涯を通して宇宙の根源にして意識の根源、さらには身体の根源に位置づけられる「法身」を求め続けた。 「空」の無限と「海」の無限、精神の無限と物質の無限、その融合。無限が一つに交わるところ、その二つの無限の間で人間は何を考え、どのように生きるのか。 空海は偉大な宗教家であった。それ以上に偉大な文学者であった。空海の宗教は空海の文学のなかにすっぽりと包み込まれる。 空海は生涯を通して、宇宙そのものである一冊の書物を書き続けていた。 あらゆるものが生まれ出てくる根源への尽きない想い。根源の場所に立つことで表現の未来がひらかれる。 空海の全貌がわかる記念碑的大著。空海とは何者なのか――日本思想史最大のオリジネーター・空海の思想に迫る。
-

古代中国の裏社会 伝説の任俠と路地裏の物語
¥1,100
版元:平凡社 著:柿沼陽平 新書版 304ページ 2025/03刊 義に厚い一方で、贋金づくりや殺人などの犯罪行為を繰り返す任俠。前漢時代の大任俠・郭解の生涯を辿りながら、彼らの実態に迫る。 約束事を重んじ、身命を賭して他人の窮状を救う一方で、殺人や強盗のほか、ニセガネ作りなどの犯罪行為にも手を染める任俠。『史記』游俠列伝で数多くの人物が取り上げられるなかで、その筆頭に挙げられるなど、司馬遷の評価が最も高い、前漢時代を生きた大任俠・郭解に焦点を当てて、古代中国社会の裏側を切り開く。 古代中国の日常の風景を描き出した著者が明らかにする、国家の法秩序の及ばない「裏」の世界とはどのようなものなのか。膨大な史料を綿密に読み込み、徹底した比較・検証をしたうえで、ストーリー仕立てにすることで読みやすさも追求した、必読の一冊。
-

イメージ、それでもなお アウシュヴィッツからもぎ取られた四枚の写真
¥2,640
版元:平凡社 著:ジョルジュ・ディディ=ユベルマン 訳:橋本一径 B6変型 408ページ 2025/05刊 監視の目を盗み、ゾンダーコマンドによって撮影された四枚の写真から、アウシュヴィッツの真理に触れることはできるのか。 もっと遠くにまで届くはずだ――アウシュヴィッツの被収容者たちが命がけで撮影して送り届けた、たった四枚のフィルムの切れ端。そこには地獄のすべてが写っているのか。クロード・ランズマンやジャン゠リュック・ゴダールとの対話を通じ、想像を絶する体験をそれでもなお想像するための微かな道を切り開く。
-

ひとが生まれる 五人の日本人の肖像
¥1,078
版元:KADOKAWA 著:鶴見俊輔 新書版 256ページ 2025年04月10日刊 彼らは「日本人」を生き抜いた――戦後を代表する思想家による極上の人生論 【ひとは社会の中の一人として、もう一度「生まれる」】 哲学から映画、マンガなど大衆文化を渉猟し、戦後日本を思索し続けた思想家、鶴見俊輔。彼が現代人の「生き方」を問い直すために選んだのは、誰もが認める偉人ではなく、社会の周縁で、時代に揉まれながら実直に生き抜いた5人の日本人だった。 明治以前に米へと越境し、日本を相対化した中浜万次郎、町村を見つめ続けた田中正造、敗北を直感しながら飛び立った林尹夫……彼らの数奇な人生をたどることで、近代日本の相貌が鮮やかに浮かび上がる。 赤川次郎氏の文庫版解説を再録。新書版解説・ブレイディみかこ