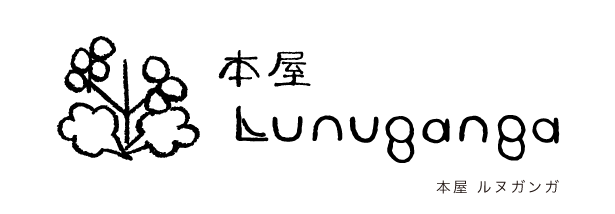-

怒っている子どもはほんとうは悲しい 「感情リテラシー」をはぐくむ
¥1,078
SOLD OUT
版元:光文社 著:渡辺弥生 新書判 296ページ 2026年1月刊 人生100年時代の現在、子どもたちに生じている心の危機。一因として「感情の理解の仕方や扱い方」を学ぶ機会に乏しい点がある。「自分の感情に気づく」「他者の気持ちを想像する」「気持ちを言葉で伝える」といった、感情に関する基礎的な力を育むことは、単に感情の安定をもたらすだけでなく、今の時代を生きる土台となる。世界でも注目のSEL(社会性と感情の学習)と感情リテラシーの育て方について第一人者が丁寧に解説。
-

社会学者が子育て本を読んで考えたこと
¥2,200
版元:慶應義塾大学出版会 著:貴戸理恵 四六判並製 224ページ 2025年10月刊 ・気鋭の社会学者が古今東西の子育て本を読み解く! ・子育て本を通して見えてくる現代の育児、そして社会とは。 小児科医や専門家による指南書、作家が自らの経験を綴ったもの、「男性の育児」を論じたもの──巷にあふれる「子育て本」とはいったい何か。自らも三児の母である社会学者が読み解く。『教育と医学』連載を書籍化。
-

それがやさしさじゃ困る
¥1,980
版元:赤々舎 著:鳥羽和久 写真:植本一子 195mm x 148mm 232ページ 2025年9月刊 子どもが自分でつかむまで! 大人が「わかったふり」をやめると、対話がはじまる。焦らず、 断ち切らず、観察しつづけるための視点──。学び・進路・日常相談と一年の日記から、関係がほどける瞬間を見つめる教育エッセイ。 『それがやさしさじゃ困る』は、子どもに向けられる「善意」や「配慮」が、時に子どもの心を傷つけ、主体性を奪ってしまうという逆説を、教育現場の最前線で20年以上子どもと向き合ってきた著者・鳥羽和久さんが鋭く描き出す一冊です。「失敗させまい」「傷つけまい」という大人の"先回り"が、実は子どもの可能性を閉ざしてしまう──。本書では「学校」「親と子」「勉強」「受験」といったテーマを軸に、現代教育の盲点と私たち大人が抱える不安の影を浮かび上がらせます。単なる批判にとどまらず、大人の葛藤や弱さへの眼差しがこめられているからこそ、その言葉は深く胸に響きます。 さらに本書を特別なものにしているのは、ページ下部に並走する一年間の日記の存在です。そこには、卒業生との忘れられない一瞬や、親子の関わりの奥に潜む無自覚な"デリカシーのなさ"への気づきなど、教育の現場で生まれた生の思索が断片的に綴られています。論として伝えられるエッセイと、濾過されない日々の記録が呼応し合い、本書は単なる教育論を超えた、立体的で豊かな手触りを届けてくれます。 解決策を提示する本ではありません。むしろ「間違うこと」「揺れ動くこと」を恐れず、子どもを信じて共に歩むことの大切さを、本書は静かに指し示しています。大人として迷い続ける私たちに寄り添い、伴走してくれる一冊です。 そして本書には、写真家・植本一子さんが鳥羽さんの教室やその周辺で撮り下ろした写真が栞のように差し挟まれています。子どもたちの表情や存在は、エッセイや日記で綴られる思索に呼応し、本書を照らし、「いま、ここ」の空気を手渡してくれるでしょう。
-

IN/SECTS vol.18 特集:THE・不登校
¥2,420
発行・編集:インセクツ A5判並製 132ページ 2025年4月刊 文部科学省発表の「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」によると不登校児童の総数は11年連続で増加、過去最多となっている。ちなみに、不登校とは、文部科学省の定義では"心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者をのぞいたもの"となっている。 今号ではその年々増加の一途を辿っている不登校について考えてみた。 そのきっかけは、編集部の周辺でも不登校児童がいる家庭が増えているという話を聞いたからだ。商売人の子、会社員の子、ライターや写真家の子、フリーランスの両親の子、様々な状況の家庭で不登校児童がいる。それは自分たちが親になったことも大きく関係しているとは思うものの、社会問題としての認識もたかまっているように思う。かくいう小誌編集長の子も不登校だ。 とはいえ、実際に当事者になってみるまで、それがどのような状況なのかはわからない。つまり知らないことが多すぎるということも今回取り上げてみたいと思った理由でもある。当事者になって初めて知る悩みや思考に加えて、不登校というと何か後ろめたい、そんな気持ちにもなるだろう。実際に、不登校児童本人もそう思っているところが少なからずあるようだ。 そこで、学校に行かないということがそもそもどのようなことなのか、不登校は後ろめたいことなのか、みんなにとって学校とは? などの考えるきっかけになればと、不登校児童の親、不登校経験者、学校の先生、そして、不登校児童を中心にいろんな人たちと話してみた。 さて、みなさんにとって学校って? 不登校とはどういうことなのか、一緒に考えてみましょう。
-

かずをはぐくむ
¥1,980
版元:福音館書店 著:森田真生 絵:西淑 四六判 216ページ 2025年4月刊 子どもと共に探し、育む、「数」の世界 「生まれたばかりの息子を初めて腕に抱いたとき、いつか彼が数をかぞえたり計算をしたりする日が来るとは、まだとても信じられなかった。言葉もない、概念もないのだ」(本書より)。しかし、やがて、子どもの心の中には数が“生まれ”、おとなと共に“育み”あうようになる。3歳と0歳のきょうだいが、8歳と5歳になるまでの驚きに満ちた日々。独立研究者、森田真生があたたかく見守り、やわらかに綴る。画家、西淑による挿絵もふんだんに掲載。
-

思春期センサー 子どもの感度、大人の感度
¥2,200
版元:岩波書店 著:岩宮恵子 四六版並製 220頁 2025/03/13刊 「いつメンはインフラ」「キャラかぶりNG」。友達関係に腐心しSNSに縛られる今どきでトラッドな思春期像を事例豊富に描く。
-

20 years of memories
¥2,750
SOLD OUT
版元:グラフィック社 イラスト:塩川いづみ A5上製 72頁 2025年3月刊 大人になったあなたへ 塩川いづみのイラストと綴る、我が子のメモリアルブック。20年間のかけがえのない思い出を書き込むことができます。今までにないシンプルでおしゃれなブックです。
-
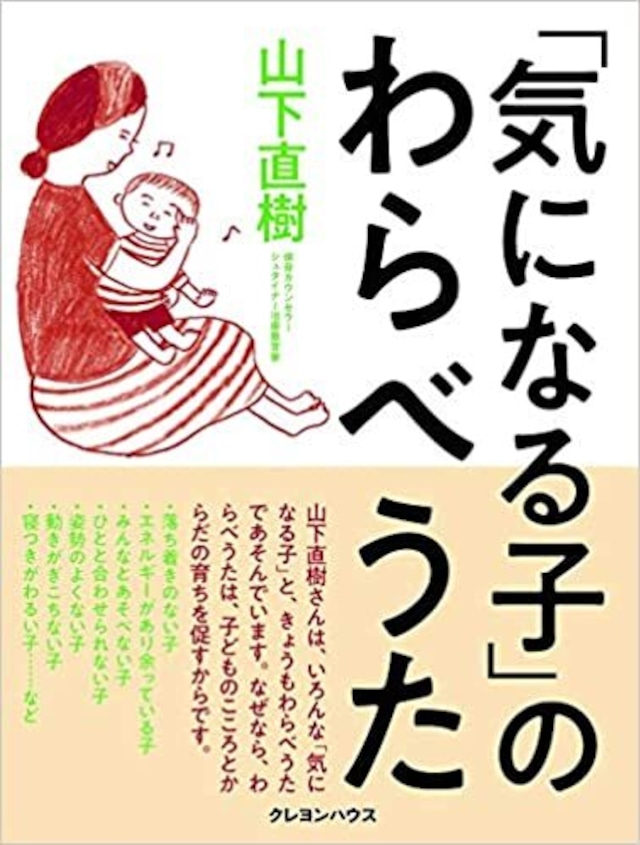
「気になる子」のわらべうた
¥1,650
山下 直樹 (著) 山下直樹さんは、いろんな「気になる子」と、きょうもわらべうたであそんでいます。なぜなら、わらべうたは、子どものこころとからだの育ちを促すからです。 [月刊クーヨン]に連載中の『「気になる子」のためのわらべうた』4年分を、特集記事と一緒に再編集! わらべうたをたのしみながら、わが子の「きになる」を変えるアドバイスが満載。保育現場だけでなく家庭でも使える、新しいわらべうた集です。 出版社 : クレヨンハウス; B5変形1版 (2018/8/27) 発売日 : 2018/8/27 言語 : 日本語 単行本(ソフトカバー) : 131ページ
-

こどもに聞かせる一日一話2
¥1,650
編集 母の友編集部 出版社(メーカー名) 福音館書店 本体価格(税抜) ¥1,500 発行日 2024/6/15 サイズ(mm) 縦220 × 横160 子どもと一緒に楽しめる、短くておもしろいお話が一挙30話! 大好評の童話集のパート2です。「幼い子と親が心をかよいあわせ、歓びをともにする有力な手がかりが、子どもに語る物語という言葉の世界にあるのではないか」。雑誌「母の友」の創刊編集長、松居直(1926~2022)はそう考え「一日一話」企画を生みだしました。本を開いて、心をつなぐひとときを。絵本『ぐりとぐら』のもととなった童話「たまご」も収録。
-

平山英三・平山和子 自然・造形・絵本の世界を歩いた二人の画家
¥4,180
絵/ 平山英三 平山和子 編者/平山日菜・杉山良子・久住和代 定価/3,800円 発行/2024年9月6日 判型/210 x 150ミリ(タテ x ヨコ) ページ数/360ページ ISBN 978-4-88411-263-9
-

こどもせいきょういくはじめます おうち性教育はじめますシリーズ
¥1,430
著・文・その他 フクチ マミ 著・文・その他 村瀬 幸浩 著・文・その他 北山 ひと美 出版社(メーカー名) KADOKAWA 本体価格(税抜) ¥1,300 発行日 2025/03/05 頁数 200 判型 A5 自分とまわりの人を大切にできる本!「せいきょういく」は、きみのこころとからだを守るためにある。知っていれば、自分のきもちをことばにして伝えられるようになるよ。 「おうち性教育はじめます」シリーズ第3弾!本書は大人から小学生へ贈るお守りコミックです。 「おうち性教育はじめます」は、1段:3~10歳の幼児期~学童期のお子さんを持つ親向け、2弾:10~18歳の思春期の子を持つ親向けとして、子どもと関わる大人の方に支持されてきました。本書は、【子どもが自分で読める本がほしい!】というたくさんの声にお応えして、小学校低学年から読める1冊にまとめました。最初に知りたい「プライベートパーツ」の話から、「誕生」や「体の変化」、バウンダリーといった人権に関わる考え方まで、これ1冊でわかります。私立和光小学校(東京都世田谷区・町田市)の教育カリキュラムを元に1~6年生までに知りたいテーマをマンガ化。巻末には、親向けの解説コラムを用意。
-

元・しくじりママが教える 不登校の子どもが本当にしてほしいこと
¥1,650
著・文・その他 鈴木 理子 出版社(メーカー名) すばる舎 本体価格(税抜) ¥1,500 発行日 2025/01/27 頁数 224 判型 46 文部科学省によれば、令和5年度の不登校の小中学生は約34万人。前年度から約4万人も増加しました。小学生の不登校は9年前の約4倍、社会に出られない若者は約40万人(高校生含む)にのぼります。最近では親子関係の悪化による痛ましい事件も目につきます。本書は子どもの不登校への対処法として、従来の子どもへのアプローチだけではなく、親の意識や思考のクセに着目しました。約600名の親・子との対話から見えてきた、不登校タイプ別の接し方について、余すところなくお伝えします。母親・父親が自らの在り方を見直し、子どもと共に未来へ向かって立ち上がるためのヒントとなる1冊です!
-

誰にも頼れない 不登校の子の親のための本
¥1,650
著・文・その他 野々はなこ 出版社(メーカー名) あさ出版 本体価格(税抜) ¥1,500 発行日 2025/02/12 頁数 296 判型 46 不登校の子どもとその親の悩みを解決する書籍。 不登校の子どもは年々増加傾向になっている。文科省の発表では、小・中学校における長期欠席者のうち、不登校児童生徒数は24万4940人(前年度19万6127人)と増加の一途を辿っており、同時に子どもの不登校に悩む親も増えている。とくに子どもが不登校になったことは親に原因があるとして自責する傾向があり、社会の理解が十分でないことから、身近な人にも悩みを打ち明けることができない親が多い。 本書は、不登校の子どもに学校社会はどう見えているのか、不登校になる原因とその段階、親が不登校児に対してすべき行動や言葉がけ、さらには進学のためのノウハウなどを提供する。著者は教員として不登校児を支えてきただけではなく、不登校になった自身の子どもと向き合って支えた経験も持つ。当事者として、不登校を支えるプロとして実践的な内容を豊富な事例とともに記載した。
-

おうち性教育はじめます 思春期と家族編
¥1,430
著・文・その他 フクチ マミ 著・文・その他 村瀬 幸浩 出版社(メーカー名) KADOKAWA 本体価格(税抜) ¥1,300 発行日 2022/12/15 頁数 272 判型 A5 10~18歳までに育む!思春期の子どもの心と体の変化から親子の距離感まで、全部マンガでわかる! 今も、そして将来離れて暮らしても。一生、子どもの絶対的な味方でいるために。親も学びの一歩をふみ出しましょう 「反抗期で何を考えているのかわからない」と親の目が届かなくなる不安や、「大学生がストーカー行為で逮捕!」などデートDVや性犯罪のニュースに心が揺れる日はありませんか?そんな時は「性教育」が助けになります。 本書は、思春期の子どもに訪れる男女の心と体の変化はもちろん、なにが暴力や性被害かを知り、自分を守るための考えを家庭で育むことができます。 18歳で成人を迎えるまであとわずか。子どもが自分の力で生き抜く力を養い、親は子の判断を受け止め、変化していく家族の関係を共に学ぶ思春期の「おうち性教育」を始めましょう。
-

中公文庫 会えてよかった
¥1,210
SBN(JAN) 9784122077393 著・文・その他 安野光雅 出版社(メーカー名) 中央公論新社 本体価格(税抜) ¥1,100 発行日 2026/01/25 頁数 328 判型 文庫 このような会い難き人に会えたのは、なんという光栄だったろう。 みんな肩書きにこだわる人ではなかったからでしょう――。 谷川俊太郎と堀内誠一との旅、「街道をゆく」挿画取材で聞いた司馬遼太郎の「千夜一夜」……。 画業から著述業まで多分野で活動し、幅広い交友関係を持つ著者が、 「会えてよかった」五十の人や出来事とのエピソードを味わい深くつづる。 〈解説〉阿川佐和子 【目次】 高峰秀子/森ミドリ/岸田衿子・今日子/松岡和子/井上ひさし/ 井上麻矢/テレビ草創期/佐藤忠良/半藤一利/澤地久枝/ 黒柳徹子/平野レミ/竹田津実/大岡信/奥本大三郎/池内紀/ 鶴見俊輔/谷川俊太郎/千住真理子/藤原正彦/村松武司/ 俵万智/大野篤美/杉本秀太郎/「日曜喫茶室」/末盛千枝子/ 司馬遼太郎/岸惠子/河合隼雄/野田弘志/森まゆみ/小沢昭一/ 板倉聖宣/有元利夫/檀ふみ/阿川佐和子/猿谷要/日高敏隆/ 森毅・野崎昭弘/「風景画を描く」/アントニ・タピエス/ 中易一郎/江國滋/堀内誠一/遠山啓・清水達雄/吉田直哉/ 「少年倶楽部」/串田孫一/関容子/絵本の世界